【閲覧注意】この記事は、子どもの虐待について触れています。
センシティブな内容を含むため、読むのがつらいと感じたら、無理をせず休んでください。
それでは、本題に入ります。
保育士ができること
虐待のサインに気づき、子どもを守るために
「この子、最近元気がないな…」
「服の下にあざがあるけど、大丈夫かな?」
「いつも眠そうにしているのは、何か理由があるのかな?」
日々子どもたちと接していると、気になることが出てくることがあります。
虐待は、子どもから「助けて」と言えないことが多い です。だからこそ、保育士が小さなサインに気づくことが、子どもを守るための第一歩 になります。
この記事では、
✅ 虐待の種類と具体的な例
✅ 虐待を受けている子どものサイン
✅ 虐待が疑われる場合の対応方法
について、できるだけ分かりやすくお話しします。
虐待には4つの種類がある
虐待には、大きく分けて4つの種類があります。
① 身体的虐待(暴力)
✅ 叩く、蹴る、殴る、火傷を負わせる などの暴力をふるうこと。
〈具体例〉
・お迎えのとき、腕を強く引っ張られている
・子どもの体に、不自然なあざや傷 がある
・「家に帰りたくない」と話すことが増えた
➡ 子どもは「怒られる自分が悪い」と思ってしまいがち なので、なかなか助けを求めません。
② ネグレクト(育児放棄)
✅ ごはんを与えない、衣服が汚れたまま、病院に連れて行かない など、子どもの基本的な世話をしないこと。
〈具体例〉
・服がいつも汚れていて、体から異臭がする
・朝ごはんを食べていない ことが多く、給食を異常にほしがる
・体調が悪そうなのに、病院に行った形跡がない
➡ 「お家でごはん食べた?」などの質問に対し、適当にはぐらかす子もいる。
③ 心理的虐待(ことばの暴力)
✅ 「お前なんかいらない」「生まれてこなければよかった」 などのことばを浴びせ、心を傷つけること。
〈具体例〉
・「どうせ自分なんて…」と 自己肯定感の低い発言 をする
・先生に褒められても、うつむいて反応しない
・家の話をしたがらず、急に黙り込む
➡ 目に見えにくい虐待だけど、子どもに深い傷を残す。
④ 性的虐待
✅ 子どもにわいせつな行為をしたり、それを見せたりすること。
〈具体例〉
・先生や友達が近づくと、体を強張らせる
・おむつ替えや着替えを 極端に嫌がる
・年齢に合わない 性的な知識や行動 がある
➡ このケースはすぐに児童相談所や警察に通報する必要がある。
虐待のサインを見逃さないために
虐待を受けている子どもは、 「自分のせいだ」「誰にも言っちゃいけない」 と思い込んでいることが多いです。
そのため、保育士が気づいてあげることが何より大切 になります。
✅ 身体的なサイン(あざ、傷、不自然な服装)
✅ 心理的なサイン(萎縮している、無気力、攻撃的)
✅ 生活習慣のサイン(給食を異常に食べたがる、体がいつも汚れている)
普段の様子と違うことが続いたら、何かあるかもしれません。
虐待が疑われたらどうする?
① まずは子どもに寄り添う
無理に聞き出さず、安心できる環境をつくることが大切。
✅ 「つらかったね」「教えてくれてありがとう」 と声をかける
✅ 「誰にも言っちゃダメ」と約束しない(専門機関に相談するため)
✅ 子どもを責めない、驚きすぎない(安心できる雰囲気を作る)
② 園内で相談する
✅ まずは園長や主任に報告 し、一緒に対応を考える
✅ 保護者にすぐに問い詰めるのはNG(子どもがさらに追い詰められる可能性がある)
③ 必要なら児童相談所や警察に通報
虐待かどうかを判断するのは専門機関の役目。
「違ったらどうしよう」と迷うよりも、「本当に虐待だったら?」と考えよう。
✅ 児童相談所(189)に相談(匿名OK)
✅ 緊急時は警察(110)へ通報
通報した人が責められることはないし、 「通報しておけば助けられたかもしれない」 という後悔をしないためにも、大切な行動になる。
まとめ:保育士ができること
✅ 子どもの変化に気づく(小さなサインを見逃さない)
✅ 安心できる関係を作る(子どもが話しやすい雰囲気を作る)
✅ 1人で抱え込まず相談する(園内で共有し、専門機関へつなぐ)
保育士は、子どもにとって安心できる存在。
だからこそ、日々の関わりの中で「守れる命」があるかもしれません。
「おかしいな?」と思ったら、ためらわずに動くこと。
それが、子どもを救う第一歩になります。
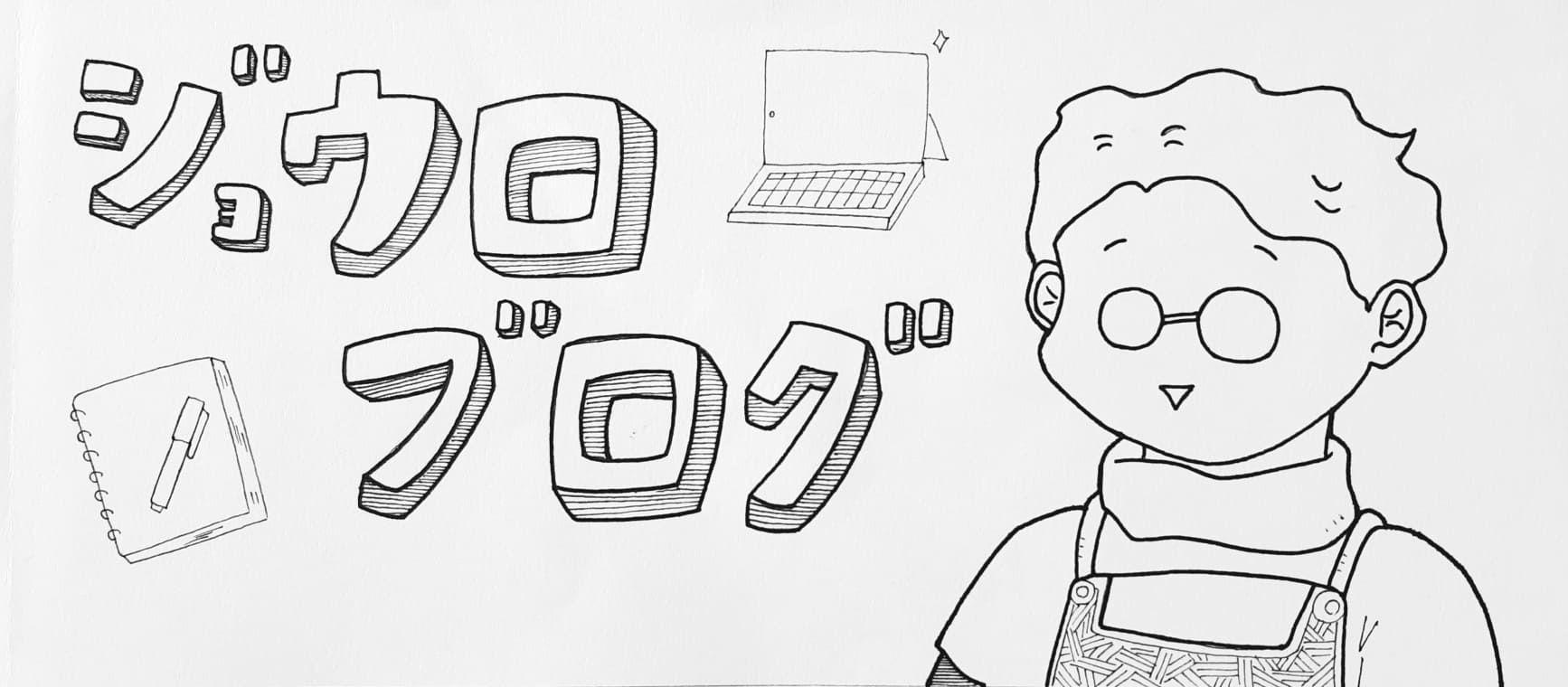




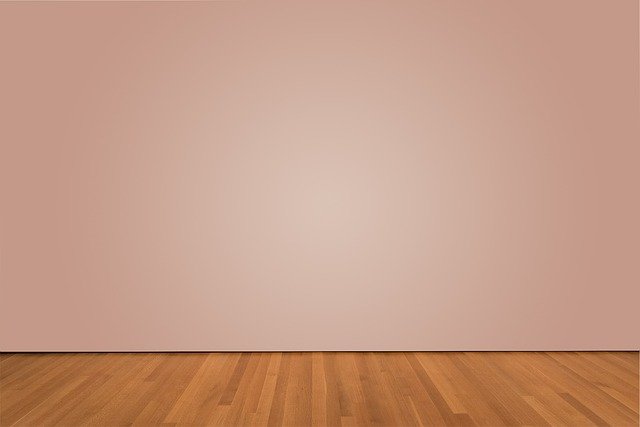


コメント