~5歳・6歳ならではの「ぶつかり合い」と、どう向き合う?~
こども園や保育園で年長さんになると、「お兄さん・お姉さんらしくなったなぁ」と感じる場面が増えてきますよね。
自分の思いをしっかり伝えられるようになったり、友だちと遊びのルールを作ったり、時には年下の子に優しく接したり…。
でもその一方で、年長児ならではのトラブルも、ぐっと増える時期です。
今回はそんなトラブルの例をいくつか取り上げながら、子どもたちの心と体の成長とどう関係しているのか、そしてそれにどう寄り添えばいいのかを考えてみたいと思います。
- 「だって○○くんがズルした!」
~ルールにこだわるようになったからこそ~
ある日、鬼ごっこの最中に「○○くん、鬼なのにタッチしなかった!ズルしてる!」と怒る年長児。
これまではなんとなく楽しんでいた遊びにも、年長さんになると「ルールを守る」ことが大事になってきます。
正義感や社会性が育ってきている証拠ですが、他の子がそのルールをうまく理解できていなかったり、少しズルをしたりすると許せなくなってしまうのです。
ポイント
年長児は「正しさ」に敏感になります
でも、全員が同じ理解度・スピードで育っているわけではありません
対応のヒント
ルールがわかりにくいときは、遊びの前にみんなで確認しておく
「どうすれば全員が楽しく遊べるかな?」と、子どもたち自身に話し合いを任せるのも効果的
- 「○○ちゃんは入れてあげない!」
~仲良しグループができるからこその悩み~
女の子に多く見られるトラブルが、「仲間外れ」です。
年長さんになると、友だち関係がより深くなり、「いつも一緒にいる○○ちゃんと遊びたい」という気持ちが強くなります。
でもその気持ちが強くなりすぎると、「他の子はいれない」という排他的な態度になってしまうことも。
ポイント
「仲良し」と「排除」の線引きがまだ曖昧
自分の気持ちを優先するあまり、相手の気持ちに気づきにくいことも
対応のヒント
「○○ちゃんと遊びたい気持ち、よくわかるよ」とまず気持ちを受け止める
その上で「みんなで遊ぶとこんな楽しいことがあるよ」と具体的な楽しさを伝えていく
誰かが傷ついていた場合は、「○○ちゃん、どう思ったかな?」と他者の気持ちを想像する練習を促す
- 「おまえバカ!きらい!」
~言葉が強くなるのは、自分の思いが強くなった証拠~
自分の思いをしっかり持てるようになってくる年長さん。
でも、その思いがうまく伝わらないとき、つい強い言葉や否定的な表現になってしまうこともあります。
たとえば遊びの途中で思い通りにいかず、「バカ!もう遊ばない!」と怒ってしまう子。
言葉を使って感情をぶつけられるようになったからこそ、逆に傷つけ合いにもなりやすくなります。
ポイント
感情と言葉が直結してしまう段階
言葉の力が強くなった分、相手への影響も大きくなる
対応のヒント
まずは「怒ってたんだね」と気持ちに寄り添う
「本当はどうしてほしかったの?」と、本心を引き出す
遊び終わったあとに「どんな言い方なら気持ちが伝わったと思う?」と振り返りの時間を持つ
- 「○○ちゃんがやったって言ってた!」
~“チクる”のか、“助けを求めている”のか~
年長さんになると、「○○くんが変なことしてたよ」と先生に伝える子も増えます。
いわゆる“チクる”という行動ですが、これもまた「ルールを守ることが大切」という意識が強くなった証でもあります。
また、自分ではどうしたらいいかわからないときに、大人に助けを求めている場合もあります。
ポイント
チクりと報告の違いをまだ理解できていない
悪気があるとは限らない
対応のヒント
「どうして教えてくれたの?」と意図を聞く
「今度はどうしたら自分で解決できるかな?」と少しずつ“自分で考える”練習を
場合によっては、「困ったときに大人に言っていいこと」と「自分で解決できそうなこと」を明確に分けて話す
- 手が出てしまう・物にあたる
~体が大きくなったからこそ、ぶつかりも大きくなる~
感情が爆発して、叩いたり押したりしてしまう。
年長児の中にも、そうした「手が出る」行動が見られることがあります。
特に男の子に多く見られる傾向ですが、背景には、自分の感情をうまくコントロールできないもどかしさがあります。
また、体が大きく力も強くなってきているので、同じ「押す」でも年中のときよりも影響が大きくなるのです。
ポイント
感情のコントロールはまだまだ発展途上
大人が「ダメ」と言うだけでは解決しない
対応のヒント
落ち着いてから、「何がイヤだったの?」と背景の気持ちを探る
感情の出口として、「言葉で伝える」「深呼吸する」「その場を離れる」など代わりの方法を一緒に考える
繰り返す場合は、その子に合った感情の整理の方法(絵に描く、砂場で遊ぶなど)を探るのも大切
まとめ:トラブルは成長のサイン
年長児のトラブルは、決して「問題行動」ではなく、心と体が育ってきた証拠です。
むしろ、こうしたぶつかり合いを通して「どうすればいいか」を学び、少しずつ社会性を育てていくのがこの時期の大切なプロセスです。
大人がやるべきことは、「ダメ!」と止めることではなく、何が起きていたのかを一緒に整理していくこと。
子どもたちの気持ちに寄り添いながら、「じゃあ次はどうする?」と未来を考える手助けをすること。
一筋縄ではいかないけれど、それぞれのトラブルの裏にある成長の芽を、一緒に育てていきたいですね。
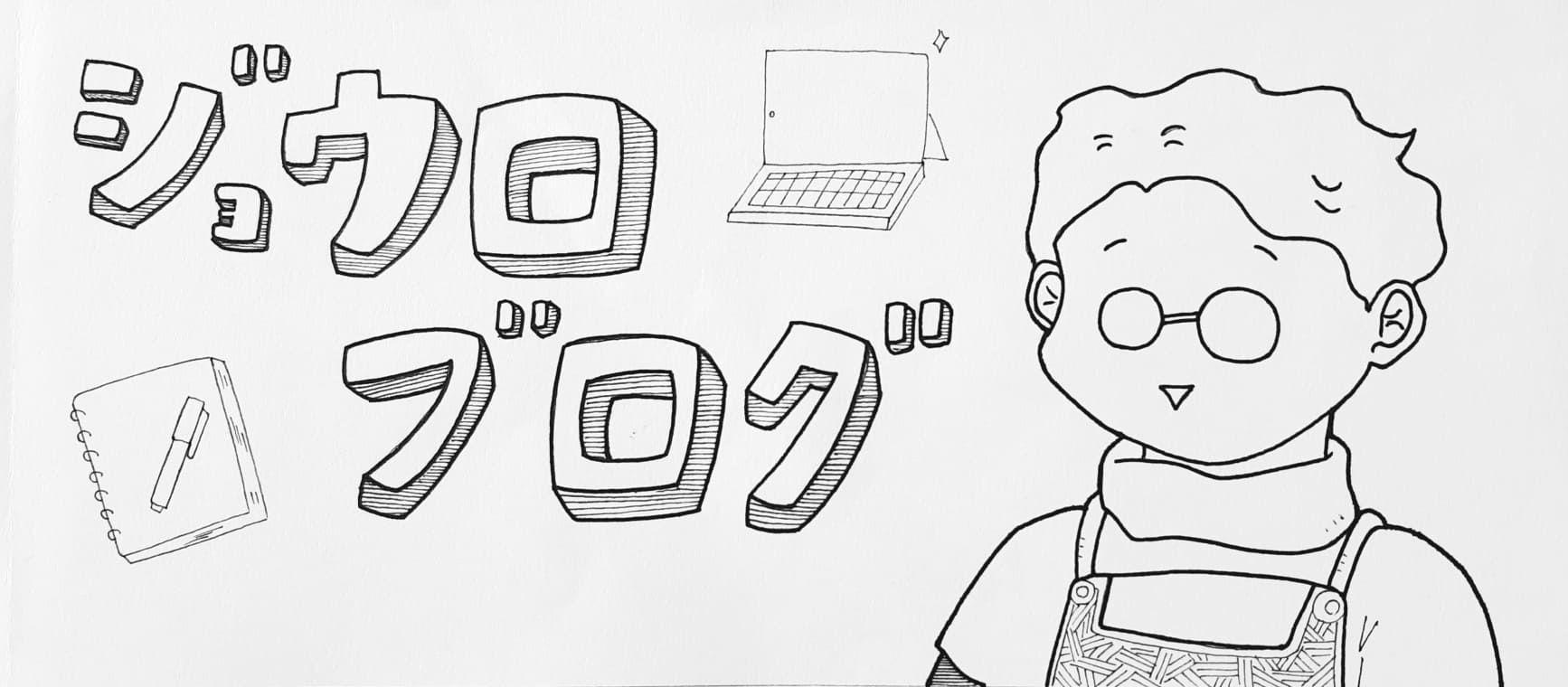







コメント