1.はじめに
保育のことを考えるとき、いつも思うのは「子どもにとって、いちばん大切な時間ってなんだろう?」という問いです。
朝から夕方まで、家族のようにすごす保育園やこども園での毎日は、子どもたちにとって「もうひとつのおうち」と言ってもいいかもしれません。
でも、その保育の現場は今、大きくゆれ動いています。
少子化がすすむ中で、なぜか保育ニーズは高まりつづけ、保育士さんは足りないまま。ICTやAIがどんどん広がる中で、「人と人」のふれあいを大切にする保育の意味も、あらためて問い直されています。
時代が変わる中で、保育もまた、変わっていくべきなのか。
それとも、変わらずに大切にしたいものがあるのか。
この問いは、保育の仕事にかかわる人だけでなく、すべての子どもたちと未来を思う人にとって、大切なテーマだと思います。
この文章では、今の保育の現場でおこっていること、これから起こりうることを見すえながら、わたしたちが「どんな保育を目指していきたいか」を考えていきたいと思います。
保育の未来をつくるのは、決して遠い世界のだれかではありません。
日々、子どもたちと向きあっているわたしたち一人ひとりが、その未来を少しずつ形にしていくのです。
2.保育の今
いま、保育の現場では何が起きているのでしょうか。
その答えを知るためには、まず「保育」という言葉がどこまでを指しているのかを見ておく必要があります。
日本では、保育を担う場所にはいくつかの種類があります。
たとえば、0〜5歳までの子どもを預かる保育園、教育が中心となる幼稚園、その両方の役割を持つ認定こども園。
それぞれの制度にはちがいがありますが、どの現場でも共通して大切にされているのが、「子どもたちの育ちを支える」という思いです。
ただ、その思いとはうらはらに、保育の現場ではさまざまな課題がふくらんでいます。
もっとも深刻なのが、保育士不足です。資格を持っていても、働いていない「潜在保育士」がたくさんいると言われています。
その背景には、仕事のたいへんさと給与のギャップがあります。
毎日たくさんの子どもと関わり、命を預かる責任を持ちながら、待遇はまだまだ十分とは言えません。
休憩も取りにくく、持ち帰りの仕事があることも多いのが現状です。
一方で、保護者との関係も、少しずつ変わってきています。
昔よりも育児について情報があふれるようになり、保護者の「こうしてほしい」「これはしないでほしい」といった希望は、とても細やかになっています。
保育者と保護者が手を取り合って子どもを育てることの大切さは変わらないものの、その関係性には、より丁寧なコミュニケーションが求められています。
また、子どもたちをとりまく環境も変わりつつあります。
都市部では園庭のない保育施設も多く、自然とふれあう時間が減っています。
一方で、外遊びを大切にしたり、自然保育を取り入れたりする園もあり、子どもにとって「いい環境とはなにか」という問いは、現場でいつも考えられています。
保育の仕事には「正解」がありません。
そのぶん、現場では日々、保育士たちが悩みながら、子ども一人ひとりに向き合っています。
遊びの中で育つ力、友だちとのやりとり、涙を流して気持ちを伝える姿…。
子どもたちは毎日、小さな一歩を踏み出しています。
そのそばにいる保育者は、ただ見守るだけではなく、ときに背中を押し、ときに手を取り、ともに歩んでいるのです。
こうした日々の積み重ねが、未来の社会をつくる力になる。
それが「今」の保育に込められた、大きな価値だと言えるのではないでしょうか。
3.社会の変化と保育の課題
わたしたちの社会は、ここ数十年で大きく姿を変えてきました。
テクノロジーの進歩や生活スタイルの変化、そして少子高齢化や家族のかたちの多様化…。
こうした社会の動きは、保育の現場にもじわじわと影響を与えています。
まず大きな変化のひとつが、「共働き世帯の増加」です。
保育園に通う子どもが増えた理由のひとつは、両親ともに働く家庭が当たり前になってきたことです。
その結果、保育園はただ「子どもを預かる場所」ではなく、「家庭の育児を支えるパートナー」としての役割をより強く求められるようになりました。
でも、だからこそ見えてくる課題もあります。
たとえば、保育の量は増えたのに、質をどう保つかという問題。
長時間保育があたりまえになる中で、子どもたちの体や心の負担はどうなっているのか。
保育者もまた、長い時間の中で子どもとどう関わり、どんなふうに遊びや生活を作っていくか、日々模索しています。
また、家庭の多様化も保育にとって大きなテーマです。
ひとり親家庭、祖父母との同居、LGBTQ+の家族、外国ルーツの子どもたち…。
これまでの「標準的な家族像」ではくくれない多くの子育てがあり、それぞれにちがった背景やニーズがあります。
保育現場では、そうした一人ひとりに向き合う柔軟さと感受性がますます求められるようになっています。
そして、もうひとつ大きな社会の変化が、「情報化社会と子どもたちの関係」です。
スマートフォンやタブレットが身近になり、大人の生活はどんどん便利になっています。
でもその一方で、「ことばがゆっくり」「人と目を合わせない」といった子どもたちの様子に、現場の保育者がちいさな変化を感じ取ることもあります。
家庭でのコミュニケーションや遊びのあり方が、子どもの育ちに影響を与えている可能性もあります。
こうした社会の流れに対して、保育現場が孤立しないことがとても大切です。
保護者や地域、行政、そして社会全体とつながりながら、子どもたちにとって本当に必要なことは何かを考えていく。
それは、保育者だけではなく、大人一人ひとりに求められていることかもしれません。
「社会の変化に流される」のではなく、「社会の中で、保育としての立ち位置を見つけていく」。
その姿勢こそが、これからの保育のあり方をささえる大きなヒントになるのではないでしょうか?
4.子どもを取り巻く新しい課題
子どもたちは、いつの時代もその時代の空気の中で育っていきます。
そして今、子どもたちを取り巻く環境は、これまでとはちがうかたちで変わりつつあります。
まず見えてくるのが、「遊び」の変化です。
昔は空き地で走り回ったり、友だちと木登りをしたり、自然の中で過ごす時間があたりまえのようにありました。
ところが今は、遊ぶ場所や時間が限られ、思いきり体を動かす機会が少なくなっています。
安全性や管理の観点から、遊びが「制限されたもの」になりつつあるのです。
その一方で、室内での遊びは増えています。
テレビ、ゲーム、タブレット…
デジタル機器は便利で楽しいものですが、そればかりに頼ってしまうと、人との関わりを通して育まれる力が育ちにくくなってしまうこともあります。
たとえば、相手の気持ちを考える力、待つ力、ケンカしても仲直りする力。
こうした「非認知能力」は、遊びの中で自然と育っていくものです。
また、ことばの発達についても新しい課題が出てきています。
家庭での会話が少なかったり、大人の忙しさから十分なやりとりが難しかったりすることで、子どもが言葉を使って気持ちを表現する力がゆっくりになることもあります。
言葉が出にくいと、相手との関係がうまくいかず、気持ちがつまってしまうこともあります。
それがかんしゃくや無気力といった行動につながる場合もあるのです。
さらに、心の安定にも注目が必要です。
保育の現場では「なんとなく元気がない」「ぼーっとしている」と感じる子が増えたという声もあります。
家庭や社会の中でのストレス、親の不安が子どもに影響している場合も少なくありません。
子どもはことばで説明できない分、行動や表情でサインを出しています。
そのサインに大人が気づけるかどうかが、とても大切です。
こうした課題に対して、保育者は日々、小さな気づきを大切にしながら子どもたちに向き合っています。
ちょっとした表情の変化、遊びの中でのやりとり、好きなこと・苦手なこと…。
一人ひとりをよく見て、その子に合った関わりを考えることが、保育の中での大事な役割です。
でも、保育だけでこれらの課題に向き合うのは限界があります。
子どもを取り巻く環境は、家庭や地域、社会全体とつながっています。
だからこそ、大人たちが一緒に子どもの育ちを支える仕組みが必要になってくるのです。
今の子どもたちは、変化の大きな時代を生きています。
その中でどれだけ安心して、のびのびと育っていけるか。
それは、わたしたち大人のまなざしと関わりにかかっているのかもしれません。
5.保育の専門性とその価値
保育という仕事には、目に見えづらいけれど、とても深い専門性があります。
子どもと遊び、生活を共にする中で、「育ち」を支えていく。
それは、知識や経験、感性、そして人としてのあたたかさが求められる仕事です。
まず、保育の専門性のひとつは、子どもの発達を見つめる力にあります。
子どもたちは、日々ほんの少しずつ成長しています。
昨日できなかったことが今日はできるようになったり、ある日突然言葉があふれたり。
そうした小さな変化に気づき、その子の今の育ちに合った関わり方をするのが、保育者の大切な仕事です。
たとえば、「靴を自分ではこうとしている」子がいたとき。
保育者はその姿をただ見ているだけではなく、
「手伝うべきか」「少し待って見守るか」「声をかけて一緒にやってみるか」など、瞬時に判断しています。
このように、子どもの行動の裏にある気持ちや育ちの段階を読み取る力は、まさに保育の専門性と言えるでしょう。
また、保育は「一人の子」を見るだけでなく、集団の中での関係性をつくる力も必要です。
子ども同士のやりとりを見守りながら、トラブルがあれば仲立ちし、でも必要以上に大人が介入しすぎないようにする。
そうしたバランス感覚もまた、保育者の腕の見せどころです。
さらに、保育の専門性は保護者や地域との関係づくりにも広がります。
家庭での様子を聞いたり、子育ての悩みに寄り添ったり、時には地域の人とつながりをつくったり。
保育者は「子どもの育ちの応援団」として、家庭や社会との橋渡し役も担っているのです。
とはいえ、保育の価値はまだまだ社会の中で十分に理解されているとは言えません。
「子どもと遊んでるだけでしょ?」「誰にでもできる仕事じゃないの?」
そんな言葉を聞いたことがある人もいるかもしれません。
でも、保育の中には、深い専門性と判断力、そして人間関係の力がぎゅっと詰まっています。
一人ひとりの子どもを大切に思い、その子の育ちを支えるという仕事は、簡単なことではありません。
むしろ、これからの社会においてますます重要になっていく仕事だと言えます。
そして何より、保育には未来を育てる力があります。
今目の前にいる子どもたちは、やがて大人になり、社会をつくっていく存在です。
その子たちが「自分って大事にされていたな」と感じられるような保育の時間は、
きっと大人になったときの心の支えになってくれるはずです。
保育者が行っている毎日の小さな積み重ねは、
子どもたちの心と体の土台をつくり、未来の社会を形づくることにつながっているのです。
6.保育者の現状と働き方
保育という仕事は、専門性も責任も高いものです。
でもその一方で、保育者が置かれている環境は、まだまだ十分とは言えません。
まず多くの保育者が感じているのが、「忙しさ」や「時間のなさ」です。
朝早くから子どもを迎え、夜遅くまで延長保育を担いながら、その合間に書類や記録の作成、行事の準備をこなす。
一日の中で「休憩らしい休憩が取れない」という声もよく聞かれます。
また、人手不足も深刻です。
保育士資格を持っていても、現場を離れてしまう人が多いのが現状です。
その理由としては、長時間労働に加え、給与の低さが大きな要因のひとつとされています。
保育者の給与水準は、他の専門職と比べても決して高くありません。
大切な命を預かり、心と体の成長を支える仕事であるにもかかわらず、それに見合った待遇が整っていないというのは、大きな課題です。
そしてもう一つ見逃せないのが、精神的な負担です。
子ども一人ひとりの気持ちを受け止めたり、保護者の悩みに寄り添ったりと、保育者は常に「人」と向き合い続けています。
ときには、感情を押し殺して対応しなければならない場面もあります。
そうした積み重ねが、心の疲れや離職につながることも少なくありません。
さらに、保育者が「社会からどのように見られているか」も、働き方に影響を与えています。
前の章でもふれたように、保育の価値や専門性が十分に理解されていないと、
「だれでもできる仕事」「遊んでいるだけ」と誤解されることがあります。
そのことで、保育者が自分の仕事に誇りを持ちづらくなることもあるのです。
しかし、こうした現状に対して、少しずつ動き始めている部分もあります。
政府や自治体が保育士の処遇改善に取り組んだり、園の中で働き方を見直そうとする動きも広がっています。
たとえば、チームで仕事を分担する体制を整えたり、ICTを活用して書類業務を軽減したり、
保育者同士の対話や振り返りの時間を大切にする園も増えてきています。
とはいえ、本質的な改善には時間がかかります。
だからこそ、今の保育者の声にしっかり耳を傾けること、
そして「保育って本当に大事な仕事なんだ」と社会全体で認識を深めることが必要です。
保育者がいきいきと働けることは、子どもたちにとっても安心できる環境につながります。
そしてそのことは、子どもたちの育ち、ひいては未来の社会の土台にもなるのです。
7.保護者・地域・社会との連携
保育という仕事は、単に園の中で子どもたちを育てるだけではなく、保護者や地域社会、さらには広い意味での社会全体との連携が不可欠です。
子どもたちは家庭や地域の中で生活し、そこでの経験が成長に大きな影響を与えます。
保育者は、その子どもたちが家庭や地域でどう過ごしているかを知り、それを踏まえて関わることが大切です。
まず、保護者との連携ですが、保育の中での成長を家庭でも理解してもらうためには、日々の情報共有が必要不可欠です。
たとえば、子どもが園でできるようになったことや、逆に困っていることを、保護者に伝えることは、子どもの育ちを支えるために非常に大事です。
また、保護者の子育てに対する悩みや不安を聞くことで、保育者はその保護者に寄り添い、共に子どもを育てるパートナーとしての役割を果たします。
こうしたコミュニケーションが円滑に行われることで、保護者と保育者の間に信頼関係が生まれ、より良い育成環境が作られます。
次に、地域との連携についてですが、地域は子どもたちにとって非常に大切な学びの場です。
地域での遊びや行事、自然との触れ合いなど、保育園外での経験も子どもたちの成長には欠かせません。
地域住民との交流や地域の行事への参加は、子どもたちに「社会の一員としての自覚」を育むきっかけになります。
保育者が地域の中で信頼され、積極的に関わることで、地域全体で子どもたちを見守り育てる姿勢が生まれます。
また、社会との連携も忘れてはいけません。
保育は単なる「子どもを預かる」仕事ではなく、未来を担う子どもたちを育む大切な仕事です。
そのため、保育者が社会全体に保育の価値を伝えることが求められます。
例えば、保育者の役割がどう重要なのか、社会全体がどのように子育てをサポートしていくべきなのかを考え、発信していくことが大切です。
保育園内の活動や行事、保育者の学びを社会に伝えることは、保育の意義を広め、社会全体で子どもを育てる意識を高める手助けになります。
そして、この三者(保護者・地域・社会)の連携が、子どもの育ちにどれほど影響を与えるかは言うまでもありません。
子どもたちが自分を大切にし、周囲の人々との関わりを大切にできるようになるためには、家庭だけ、園だけ、地域だけではなく、全体で育てる意識が必要です。
保育者、保護者、地域の人々、そして広い社会が一体となって子どもを見守り育てていくことが、子どもたちの健やかな成長を促す最も効果的な方法です。
8.未来の保育に向けた改革と展望
保育は常に進化している分野であり、今後さらに多くの改革が期待されます。
少子化や共働き家庭の増加、技術の進展など、社会全体の変化に伴い、保育のあり方も大きく変わる必要があります。
ここでは、未来の保育がどのように変わり、どのような展望が待っているのかについて考えます。
- テクノロジーの導入と活用
未来の保育には、テクノロジーが重要な役割を果たすことになるでしょう。
AIやロボット、IoT(モノのインターネット)技術の進化により、保育の現場での業務効率化や、子どもたちとの新しい関わり方が可能になると考えられます。
たとえば、子どもの発達の記録や保護者とのコミュニケーションをデジタル化し、手間を省くと同時に、より効率的に情報を共有することができます。
また、AIを使った個別の学習支援や、ロボットによる遊びのサポートが子どもたちの興味を引き、発達を促すツールとして活用される日が来るかもしれません。
もちろん、テクノロジーの利用には注意が必要ですが、うまく取り入れることで、保育の質を向上させる大きな可能性を秘めています。
- 保育者の専門性の向上と働き方改革
未来の保育においては、保育者の専門性の向上と、より良い働き方の確立が不可欠です。
現在の保育者は、高い専門知識と技術を持ちながらも、長時間労働や低い賃金に悩まされることが多いのが現状です。
これからは、保育者が自分の成長を感じながら、健やかな環境で働けるようにするための改革が進むことが予想されます。
例えば、保育者の専門性を高めるための教育や研修がさらに充実し、資格取得やキャリアアップの機会が広がるでしょう。また、働きやすい環境作りが進むことで、保育士の離職率が低下し、より多くの人が長く保育の仕事に携わることができるようになります。
働き方改革の一環として、フレキシブルな勤務時間や、保育士同士の協力体制の強化、心理的サポートの充実などが実現することで、保育者が安心して働ける環境が整っていくでしょう。
- 子どもの多様性に対応した保育
未来の保育は、子どもたち一人ひとりの個性や多様性にもっと焦点を当てるようになるでしょう。
今日の社会では、子どもたちの家庭環境や育ち方、学び方が多様化しています。
このような中で、保育者は、すべての子どもがその可能性を最大限に発揮できるよう支援することが求められます。
たとえば、特別な支援が必要な子どもや、異なる文化的背景を持つ子どもに対しても、それぞれに合ったサポートが提供されるようなインクルーシブな保育が進むと考えられます。
また、学びの方法も多様化し、遊びやプロジェクト型学習を通じて、子どもたちが自分の興味を深めることができるような環境が整備されるでしょう。
こうした柔軟な対応ができる保育者を育てるための教育システムの改革も、今後ますます重要になってきます。
- 保育施設のあり方の進化
未来の保育施設は、もっと子ども中心の、柔軟で創造的な空間に進化していくと予想されます。
これからは、保育施設がただの「預かり場所」ではなく、子どもの成長を支える大切な場所であるという認識が広がります。
そのため、施設の設計や運営方法も変わり、もっと自然環境や地域とのつながりを重視した形が増えていくでしょう。
たとえば、園庭や室内の環境が、より自由な遊びや探索を促進できるようにデザインされるほか、地域の自然や文化と積極的に接する機会が増え、子どもたちが地域の一員として育つ機会が提供されます。
また、保育施設の運営においても、保護者や地域の参加を促す共同体感覚を大切にしたモデルが広がり、より多くの人々が子どもの成長を支える役割を担うようになるでしょう。
このように、未来の保育は大きく変わっていくことが予想されますが、どんな改革が行われても、「子どもの最善の利益」が最優先にされることが重要です。
今後の保育がより良い方向に進むためには、私たち一人ひとりが保育の価値を理解し、支えていく意識を持つことが欠かせません。
未来の保育は、子どもたちが豊かな社会を築くための礎として、ますます重要な役割を担っていくことでしょう。
9.終わりに
保育の未来には、さまざまな変革と挑戦が待ち受けています。しかし、最も大切なのは、子どもたちの最善の利益を最優先に考えることです。
これからの社会では、保育の役割がますます重要になり、保育者や保護者、地域社会が協力し合い、子どもたちを育てていく環境が整備されるでしょう。
- 保育の価値を再認識
未来の保育においては、テクノロジーの導入や保育者の専門性の向上、そして働き方改革が進み、より良い環境が提供されることが期待されます。
また、子どもたち一人ひとりの個性を尊重し、多様性に対応した保育が進むことで、子どもたちが自分らしさを大切にしながら成長する社会が築かれるでしょう。
- つながりの重要性
保育者、保護者、地域社会、そして広い社会が一体となり、子どもたちを支える意識が広がることが、今後ますます求められます。
保育は単なる「預かり」の場ではなく、子どもたちの未来を作る大切な場であり、社会全体でその価値を支え、広めていく必要があります。
- 持続可能な保育の実現
未来の保育が持続可能であるためには、保育者の待遇向上や、保育環境の改善が欠かせません。
また、社会全体で保育を支える意識を高め、子どもたちにとって最良の育ちの場を提供するために、私たち一人ひとりがその役割を担っていくことが求められます。
保育の未来は、子どもたちの未来とも言えます。
そのため、私たちは今のうちから保育の価値を深く理解し、共に育て合う社会を作っていくための努力を惜しむべきではありません。
子どもたちがより良い未来を築くためには、今の保育がどれだけ充実したものであるかが重要です。
私たちの手の中にあるのは、未来をつくる力です。だからこそ、保育を支えるすべての人々が一丸となり、子どもたちの成長を共に見守り育てていく責任があると言えるでしょう。
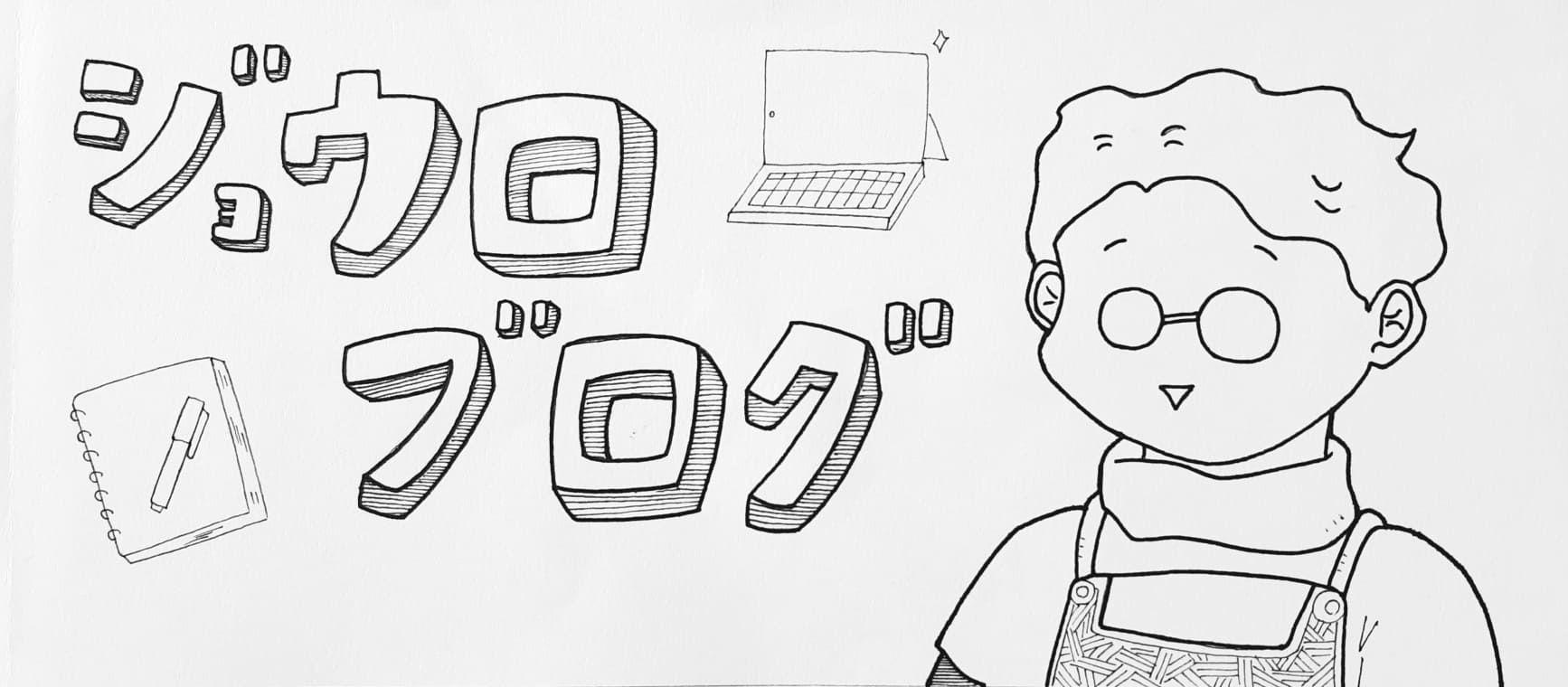







コメント