第1章:「なんで?」は子どもたちからのプレゼント
「先生、なんでドキドキしてるの?」年少さんの子どもが、自分の胸に手を当てながらそう尋ねてきたことがあります。心臓の音を聞きながら、ふとした疑問がわいてきたのでしょう。大人にとっては当たり前に感じる身体の働きも、子どもにとってはまるでミステリー。こんな問いかけがあった日は、保育の時間がよりいっそう色鮮やかに感じられます。子どもたちは毎日、「なんで?」「どうして?」と世界に問いかけながら過ごしています。その目はキラキラしていて、大人がすっかり忘れてしまったような探求心で満ちています。一方で、大人はときに困ってしまうこともあります。たとえば、「おしっこってなんで黄色いの?」「なんでウンチってくさいの?」「ブラックホールってどうやってできるの?」こうした問いに、すぐに答えられる大人は少ないかもしれません。特に科学や体の仕組み、宇宙のこととなると、言葉に詰まってしまうことも。でも、実はそこが大切なポイントなのです。
第2章:正しい答えより、大事なもの
子どもの質問に対して、大人がすぐに答えられないと「申し訳ない」「ちゃんと教えてあげられなかった」と感じてしまうことがあります。でも実は、子どもにとって「正しい答え」よりも、ずっと大切なことがあります。それは、大人がその問いにどう向き合うかという“姿勢”です。たとえば、「ブラックホールってなんでできるの?」という問い。私は正直その場では何も言えませんでした。でも、「先生もよくわからないなあ。一緒に調べてみようか」と返したとき、子どもがパッと嬉しそうな顔をしたのです。大人が一緒に考えてくれる。それだけで、子どもにとっては大きな安心と喜びにつながります。「なんで?」に真剣に向き合ってくれる大人がいる。これは、子どもにとって「自分の気持ちが大事にされている」と感じられる瞬間です。子どもの「なんで?」に向き合う3つのコツ1. まずは受けとめる「いい質問だね」「面白いことに気づいたね」など、子どもの気づきを肯定的に返します。2. わからないことは一緒に調べる無理に正解を出そうとせず、「あとで調べてみよう」「図鑑で見てみようか」と一緒に考えるスタンスを大切にします。3. やさしい言葉とイメージで伝えるたとえば「心臓はポンプみたいに血を送ってるんだよ」「おしっこの色は、体の中でいらなくなったものの色なんだよ」など、子どもが想像しやすい言葉に置きかえて伝えます。正しいかどうか以上に、「一緒に考えてくれる」「聞いてくれてうれしい」という体験が、子どもにとって大きな学びとなっていきます。
第3章:子どもの問いは、想像力を育てる種
「なんでおしっこは黄色いの?」
子どもたちの「なんで?」には、時として大人も驚くようなユニークな質問があります。これは、単なる好奇心や疑問にとどまらず、子どもの想像力や探求心が育まれている証拠です。子どもたちは、世界の仕組みや自分の体について知りたがり、日々新たな発見をしているのです。
子どもにとっての「なんで?」の意味
「なんで?」という問いかけは、単に知識を得るためのものではありません。もっと根本的な意味があります。それは、「世界を理解したい」「自分と世界との関係を知りたい」という欲求から来ているのです。子どもたちが「おしっこはどうして黄色いの?」と尋ねるのは、その仕組みを知りたいというよりも、心や体の不思議を感じ、それを他者と共有したいという思いからきていることが多いのです。
だからこそ、答えるときに大人は「なるほど、こんなことを気づいているんだ!」と、その発想を大切にする姿勢が大事です。子どもの問いに対して否定することなく、「面白いね」「一緒に考えてみよう」と受け入れることで、子どもは自分の感覚をさらに深め、次の問いを生むきっかけとなります。
どうして想像力が育つのか?
「おしっこが黄色い理由」「心臓がドキドキする仕組み」といった体の不思議から、宇宙のこと、時間や空間の概念にまで至る問いかけ。それらにどう向き合うかによって、子どもたちの想像力はどんどん育っていきます。興味を持ったことをもっと知りたいという欲求は、創造性や思考力、さらには問題解決能力を育むための種となるのです。
例えば、「ブラックホールってどうしてできるの?」という問いに対して、答えがすぐに出てこなくても、「一緒に調べてみようか」という姿勢を示すだけで、子どもは自分の疑問を解決するために必要な方法や手段を考え始めます。調べる過程で出会う新しい発見が、想像力を広げ、次々に新しい「なんで?」を生むのです。
子どもの問いが育む想像力の育て方
- 問いを尊重する
子どもの問いを簡単に答えずに、「なんで?」を深堀りしていくことで、子どもの想像力が豊かになります。例えば、「どうしておしっこは黄色いの?」に対して「それは体がいらなくなったものを捨てるからだよ」と言うだけでなく、「じゃあ、体は他にどんなことをしているのかな?」と話を広げていきます。 - 創造的に答える
「おしっこはどうして黄色いの?」と聞かれたら、「それは体の中の小さな工場が働いて、いらないものを黄色にして出しているんだよ」というように、子どもがイメージしやすいような表現を使ってみましょう。子どもはその後、自分の体に対しての関心が増し、他の疑問を生み出します。 - 一緒に考える姿勢を持つ
子どもの問いには、必ず一緒に考えるという姿勢が大切です。「わからないことは一緒に調べよう」「調べてみたら、こんなことがわかったよ!」という形で、一緒に学び合う時間を作ることで、子どもはさらに積極的に問いを発するようになります。
子どもたちの「なんで?」は、ただの質問ではありません。それは彼らの好奇心を育み、世界を深く知るための第一歩。私たち大人がその問いにどう向き合うかで、子どもたちの学びがどんどん広がっていきます。問いかけが続く限り、子どもたちの想像力は無限に広がっていくことでしょう。
第4章:「わからないね」を言える勇気が、子どもの未来を変える
「どうしてブラックホールができるの?」
年長の子にそう聞かれたとき、私は正直に「わからないなあ」と答えました。
するとその子は、私の顔をじっと見たあと、ニコッと笑って「じゃあ一緒に図鑑で調べてみる?」と言いました。
このとき私は思いました。「知らないことを知らないって言えること」が、子どもとの信頼を深め、学びの扉を開くんだ、と。
大人は、つい「教えなきゃ」「ちゃんと説明しなきゃ」と気負ってしまいます。でも、子どもにとって大切なのは、“大人が正しく答えること”ではなく、“自分の疑問を一緒に考えてくれる人がいること”なんです。
「わからない」は恥ずかしくない
むしろ、「わからない」と正直に言えることは、大人としての強さです。それは子どもに、「知らないことは調べていい」「考えていい」「一緒に学べばいい」という姿勢を見せることでもあります。
この姿勢は、子どもにとってとても重要です。
・わからないことに出会ったときに逃げない力
・知りたいと思ったときに自分で調べる力
・答えのない問いを楽しむ力
これらはすべて、「大人が一緒に考えてくれた経験」の中で育まれていくのです。
未来へつながる対話の種
子どもたちの問いに、完璧に答える必要はありません。
大切なのは、その問いを一緒に味わい、一緒に悩み、一緒に「へえ、そうなんだ」と驚けること。
問いの中にこそ、学びがあり、対話があり、信頼がある。
そうして育まれた“学びあう関係性”は、きっとその子が大きくなったときにも、「自分はちゃんと聞いてもらえた」「一緒に考えてくれる人がいた」という確かな経験として残るはずです。
だからこそ、子どもの「なんで?」に出会ったら、ぜひ一言。
「先生もわからないな。いっしょに考えてみようか」
その小さなひと言が、子どもにとっては、大きな「未来への贈り物」になるのです。
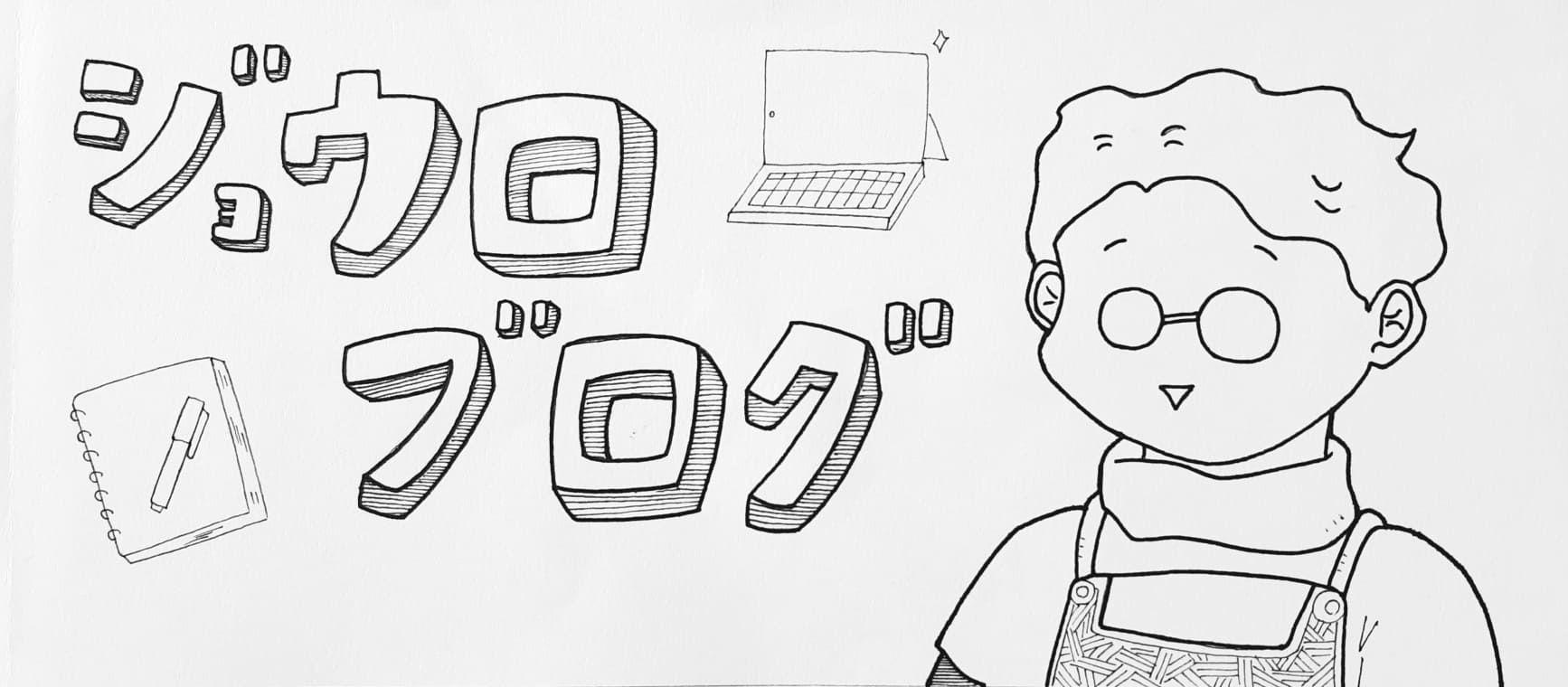







コメント