1.はじめに(導入)
こどもと過ごしていると、「これはちゃんと伝えなきゃな」と思う場面がたくさんあります。そんなときに出てくるのが「叱る」という行動。でも、「ちゃんと伝えたい」と思えば思うほど、つい感情的になってしまったり、あとから「言いすぎたかな…」と反省してしまったりすること、ありませんか?
叱ること自体がいけないのではなく、大切なのは「どう伝えるか」。そして実は、叱る前にちょっとした「準備」ができていると、こどもにも自分にもやさしくなれることがあります。
このページでは、「こどもを叱るって、どうしたらいいんだろう?」と感じたときに思い出してもらえるような、やさしいヒントをまとめてみました。保育の現場や、家庭での子育てのなかで、誰かの心が少し軽くなるように、そんな気持ちで書いています。
2.「叱る」と「怒る」はちがう
こどもに何かを伝えたいとき、私たちはつい強い口調になってしまうことがあります。そんなとき、自分でも「今のは怒っちゃったな…」と感じることってありませんか?
まず大切なのは、「叱る」と「怒る」はちがう、ということを知っておくことです。
「怒る」は、大人の気持ちがあふれてしまった状態。イライラや焦り、不安など、こちらの感情がそのまま言葉になってしまうことが多いです。一方で、「叱る」は、こどもに「どうしてそれがよくないのか」「どうすればよかったのか」を伝え、学びにつなげるための行動です。
たとえば、友だちをたたいてしまった子に対して、「なんでそんなことするの!やめなさい!」と怒るだけでは、こどもには「怖かった」という記憶だけが残ってしまいます。でも、「たたかれたら悲しい気持ちになるよ。手はお話を伝えるために使おうね」と伝えることで、その子は次にどう行動すればいいのかを考えるきっかけをもらえます。
そしてもうひとつ大事なのが、「叱るときの一貫性」です。
たとえば、あらかじめ「おもちゃは順番で使おうね」とこどもと約束していたとします。もしその約束を破ってしまったときに「どうして守れなかったのか」「次はどうしようか」を一緒に考えることで、こどもは「これは守るべきことなんだ」と理解できます。
でも、昨日はスルーしたのに今日は叱られる…となると、こどもは「なんで今日はダメなの?」と混乱してしまいます。だからこそ、「こういうときは叱る」「約束を破ったときは伝える」といった、わかりやすいルールを日ごろから共有しておくことが大切です。
叱ることは、こどもが自分の行動を振り返るチャンス。そして、大人にとっても「どう伝えよう?」と考えることで、自分の感情や関わり方を見直すきっかけになります。一貫性のある関わりは、こどもに安心感も与えてくれます。
3.叱る前にできる「心の準備」
こどもに「これは伝えなきゃ」と感じたとき、すぐに言葉をぶつける前に、少しだけ立ち止まってみることも大切です。叱る前のちょっとした「心の準備」で、伝え方がグッとやさしくなったり、こどもが受け取りやすくなったりします。
まずは自分の気持ちを整える
私たちは忙しい日々のなかで、つい余裕をなくしてしまいがちです。そんなときに起こったこどもの困った行動には、どうしても強い反応をしてしまうことがあります。
そんなときこそ、まずは深呼吸をひとつ。自分の気持ちを落ち着けるだけでも、言葉選びや声のトーンが変わります。
「この子はどうしてこうしたんだろう?」
「もしかして、何か困っているのかもしれないな」
そんなふうに、こどもの気持ちを想像するだけでも、伝え方は変わってきます。
背景に目を向ける
こどもの行動には、かならず何かしらの理由があります。お友だちを押してしまった子がいたとして、「ただ悪いことをした」のではなく、「遊びたかったのにうまく言えなかった」とか「眠くてイライラしていた」など、背景に気づくことで、その子に合った関わり方が見えてくることもあります。
叱るときにその理由を全部聞き出す必要はありません。でも、大人が「きっと何かあるんだろうな」と思って関わるだけで、叱り方が「責める」ものから「支える」ものに変わります。
事前に「約束」をしておく
実は、叱らないための一番の準備は、あらかじめルールや約束を伝えておくことかもしれません。
「おやつはテーブルで食べようね」
「おもちゃは順番に使おうね」
こんなふうに、こどもがわかりやすい言葉で、日ごろからルールを共有しておくと、「それは約束だったよね」と伝えやすくなります。こどもにとっても「なにがダメだったのか」がはっきりするので、納得しやすくなります。
このときに気をつけたいのは、大人の対応がブレないこと。昨日は見逃したのに、今日は厳しく叱られる…というように、ルールが日によって変わると、こどもは混乱してしまいます。
「約束したことは守る」「守れなかったときはきちんと伝える」
そんな一貫した関わりが、こどもに安心感と信頼感を育てていきます。
4.叱るときのポイント
こどもに何かを伝えるとき、大人の「伝えたい気持ち」が先に立ってしまうと、どうしても一方通行になってしまいがちです。ここでは、こどもがちゃんと受け取れるようにするための「叱るときのポイント」を紹介します。
- 短く、わかりやすく伝える
こどもはまだ、長い話や複雑な表現を理解するのがむずかしいことがあります。だからこそ、伝えたいことはシンプルに、できれば一文で伝えることを意識してみましょう。
たとえば、「走ったら転んであぶないよ」や「順番を守ろうね」といった、短くて具体的な言葉が伝わりやすいです。
ダメな理由をくどくど説明したり、「何回言ったらわかるの!」と過去を持ち出したりすると、こどもは途中で心を閉じてしまいます。
- 人格ではなく、行動に目を向ける
叱るときに気をつけたいのが、「あなたって本当にわがままね」など、こどもの性格や人格を否定する言葉を使ってしまわないことです。
「順番を守らなかったのはよくなかったね」
「たたくのはだめだよ。ことばで伝えようね」
このように、行動そのものにフォーカスして伝えると、こどもも「次はこうすればいいんだ」と前向きに受けとりやすくなります。
人格を否定されると、「どうせぼくはダメなんだ」と自己肯定感が下がってしまうこともあるので、やさしく丁寧に伝えることが大切です。
- タイミングに気をつける
叱るタイミングも、意外と大切なポイントです。
こどもが興奮していたり、泣いていたりするタイミングでは、話を聞ける状態ではないことが多いです。そんなときは、少し落ち着いてから話す方が、しっかり気持ちを伝えられます。
また、みんなの前で叱ると、恥ずかしさや反発心が強くなってしまうことも。できるだけ人目のないところで、落ち着いた声で伝えることが、こどもとの信頼関係を守るコツです。
- 最後に「信じているよ」のメッセージを
叱ったあとは、ぜひ「またがんばろうね」「大丈夫だよ、ちゃんと見てるよ」といった、あたたかいひと言を添えてあげてください。
こどもは、大人に叱られることで「もう嫌われたかも」と不安になることがあります。でも、叱ったあとに「見守っているよ」「応援しているよ」という気持ちが伝わると、安心して自分を振り返ることができるのです。
叱るというのは、大人の想いをこどもに届ける大事な時間。でもそれは、こどもをコントロールするためではなく、こどもがよりよく育つためのサポートです。
そのために、言葉の選び方やタイミングをちょっと工夫してみるだけで、こどもとの関係がぐっとあたたかくなりますよ。
5.叱ったあとのフォローと関係づくり
叱るということは、こどもにとっても大人にとっても、心が少しゆれる体験です。だからこそ、「叱ったあとの時間」をどう過ごすかが、とても大切になってきます。
ここでは、叱ったあとのフォローのしかたや、こどもとの関係を深めていくためのヒントを紹介します。
気持ちの回復を待つ時間
叱られた直後のこどもは、少し傷ついたり、不安になっていることがあります。そんなときは、無理に話を続けたりせず、そっと近くで見守る時間を持つのもひとつの方法です。
しばらくして落ち着いてきたら、こどもの方から何か話し出すこともあるかもしれません。大人が焦らずに待ってあげることで、こどもは「気持ちを整理する力」を育んでいくことができます。
普段どおりに接することの大切さ
叱ったあとにギクシャクした空気が続くと、こどもは「まだ怒られてるのかな」と不安になってしまいます。
だからこそ、叱ったあとはできるだけ普段どおりに接することが大切です。
「もう終わったよ、大丈夫」というメッセージを、表情やふるまいで伝えてあげましょう。
たとえば、おやつの時間に「おいしいね」と笑いかけたり、遊びの中で軽くタッチしたり。ちょっとした関わりが、「ちゃんと受け入れてもらえてる」という安心感につながります。
一緒にふり返る時間をつくる
少し時間がたったあとで、「さっきのこと、どう思った?」と、ふり返りの時間を持てると理想的です。
大事なのは、こどもを問い詰めるのではなく、「自分で考えてみる時間」を一緒に過ごすこと。「どうしたらよかったかな?」「今度はどうしたい?」という問いかけを通して、こどもは自分で考える力を育てていきます。
正解を教えすぎず、こどもの言葉に耳を傾けることで、「自分で考えて行動できる子」に近づいていきます。
関係は「叱ったあと」に深まる
叱ることは、「愛情があるからこそ」の行動です。でも、それがこどもにちゃんと伝わるのは、叱ったあとにどう関わるかにかかっています。
大切なのは、「伝えたうえで、なお見守る姿勢」です。
こどもにとって「叱られても嫌われなかった」「ちゃんと信じてもらえてる」という実感は、自己肯定感を育てる大きな土台になります。
叱ったあとに、ちょっと手を添えるようなフォローをする。
それだけで、こどもとの関係はもっとあたたかく、信頼に満ちたものになっていきます。
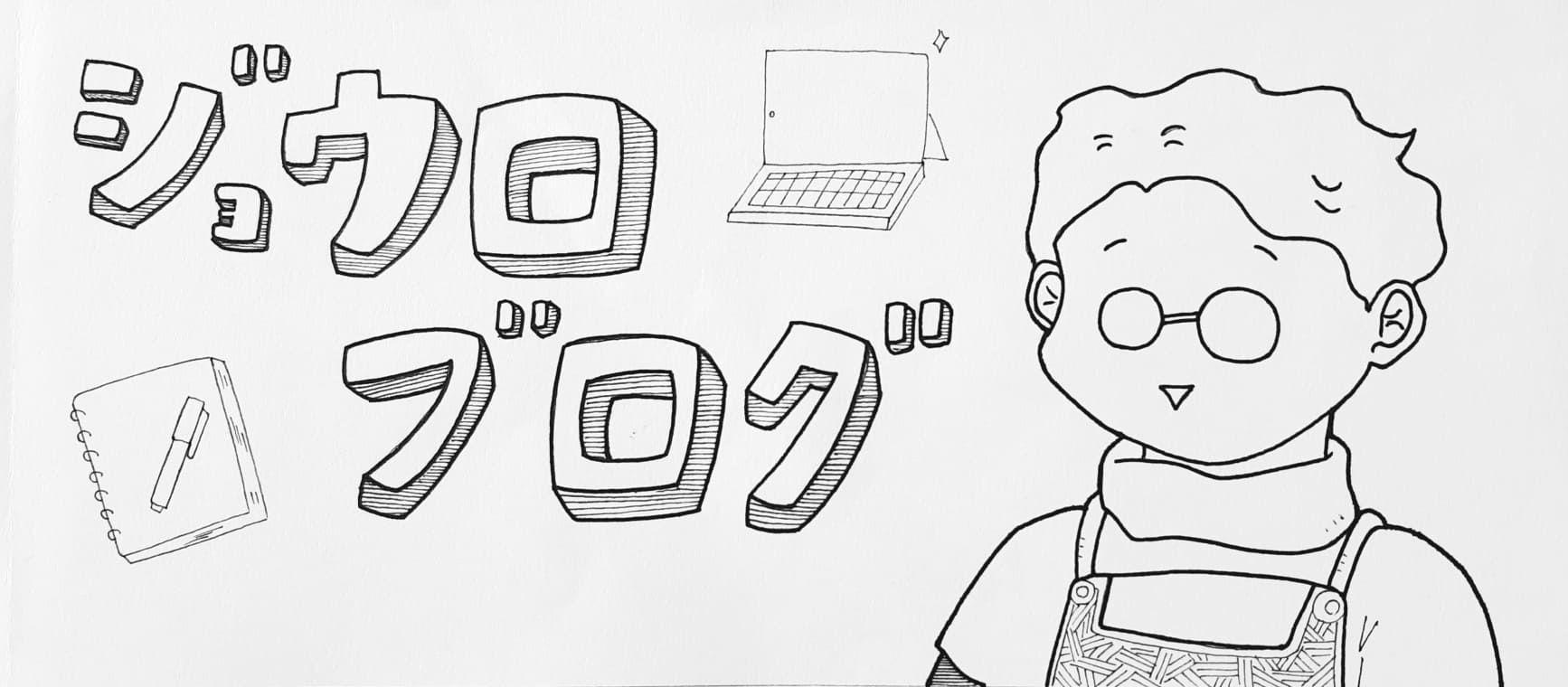







コメント