保育の現場では、子どもたちが元気いっぱいに遊び、学びながら成長していきます。しかし、その一方で、思わぬ事故が起こることもあります。先生たちが日頃から安全対策を意識し、環境を整えることで、防げる事故はたくさんあります。本記事では、園での事故防止と安全対策について、具体的なポイントをまとめます。
- 環境の安全確認
室内のチェックポイント
家具や遊具の配置:転倒しやすいものは固定することが大切です。例えば、本棚が子どもに倒れてこないよう壁に固定したり、角のある机にはクッション材をつけると安心です。
床の状態:滑りやすい場所がないか、床に物が落ちていないかを確認します。例えば、冬場の加湿器の水漏れで床が濡れて滑りやすくなることがあるため、こまめにチェックしましょう。
電気コードやコンセント:子どもの手が届かないようにし、コードに足を引っかけない工夫をすることが大切です。例えば、コードをまとめて壁に沿わせると、遊び中の転倒リスクが減ります。
扉や窓:指を挟まないようストッパーをつけることが有効です。特に、ドアが強く閉まる園では、ドアクッションを活用すると安心です。
園庭や屋外のチェックポイント
遊具の安全点検:破損やサビ、ぐらつきがないかを定期的に確認します。例えば、ブランコのチェーンが緩んでいないか、すべり台の接合部分に隙間ができていないかをチェックするとよいでしょう。
地面の状態:でこぼこがないか、ぬかるんでいないかをチェックします。例えば、大雨の翌日は地面がぬかるみやすく、走ると転倒する可能性があるため、遊び方を工夫しましょう。
植物の管理:有害な植物がないか確認し、子どもが触れても安全な環境を整えます。例えば、園庭にアジサイがある場合、誤って口に入れないように手の届かない場所に移すのが良いでしょう。
門やフェンス:子どもが勝手に外に出られないか、鍵がきちんとかかるかを確認します。特に、送迎時は門が開いたままになりがちなので、職員が交代で確認すると安心です。
- 事故を防ぐためのルール作り
活動中のルール
走る場所と歩く場所を決める:室内では走らない、園庭では周りをよく見て遊ぶよう指導します。例えば、廊下で鬼ごっこをして転んでしまうことがあるため、遊びは園庭だけにするなどのルールを決めると良いでしょう。
おもちゃの使い方を教える:投げない、踏まない、順番を守ることが大切です。例えば、積み木を投げると友だちに当たってケガをすることがあるため、遊ぶ前にルールを確認しましょう。
手洗い・消毒の徹底:感染症予防のために手洗いの習慣をつけます。例えば、給食の前や外遊びの後に「手をきれいにしてから食べようね」と声かけをすると、自然と習慣になります。
給食・おやつのルール
アレルギー対応:該当の子どもの食事内容を事前に確認し、誤食を防ぎます。例えば、アレルギーのある子どもには、名前入りのトレイを使って誤配を防ぐ工夫ができます。
食事中の姿勢:しっかり座って食べるよう指導し、歩きながら食べないようにします。例えば、座らずに食べると誤嚥のリスクがあるため、着席してから食べ始めるルールを徹底しましょう。
誤嚥(ごえん)対策:小さい食材は細かく切る、よく噛んで食べるよう促します。例えば、ぶどうは丸ごとではなく半分に切ることで、のどに詰まりにくくなります。
- 事故が起きたときの対応
ケガの対応
すぐに応急処置をする:消毒、止血、冷却など適切な処置を行います。例えば、転倒してすり傷ができた場合は、流水で洗い、清潔なガーゼで覆うと良いです。
保護者への連絡:状況を正確に伝え、必要に応じて受診をすすめます。例えば、打撲がひどい場合は、「腫れがあるので病院で診てもらうと安心です」と伝えるとよいでしょう。
緊急時の対応
避難経路を把握する:火災や地震などの避難ルートを日頃から確認しておきます。例えば、非常口の場所を子どもたちと一緒に確認する訓練をすると、実際の場面で落ち着いて行動できます。
まとめ
園での事故防止と安全対策は、日々の小さな心がけの積み重ねです。環境を整え、ルールを守り、適切な対応を身につけることで、子どもたちが安心して過ごせる場所を作ることができます。先生たち一人ひとりの意識が、園全体の安全につながります。ぜひ、今日からできることを実践し、事故のない園づくりを目指しましょう。
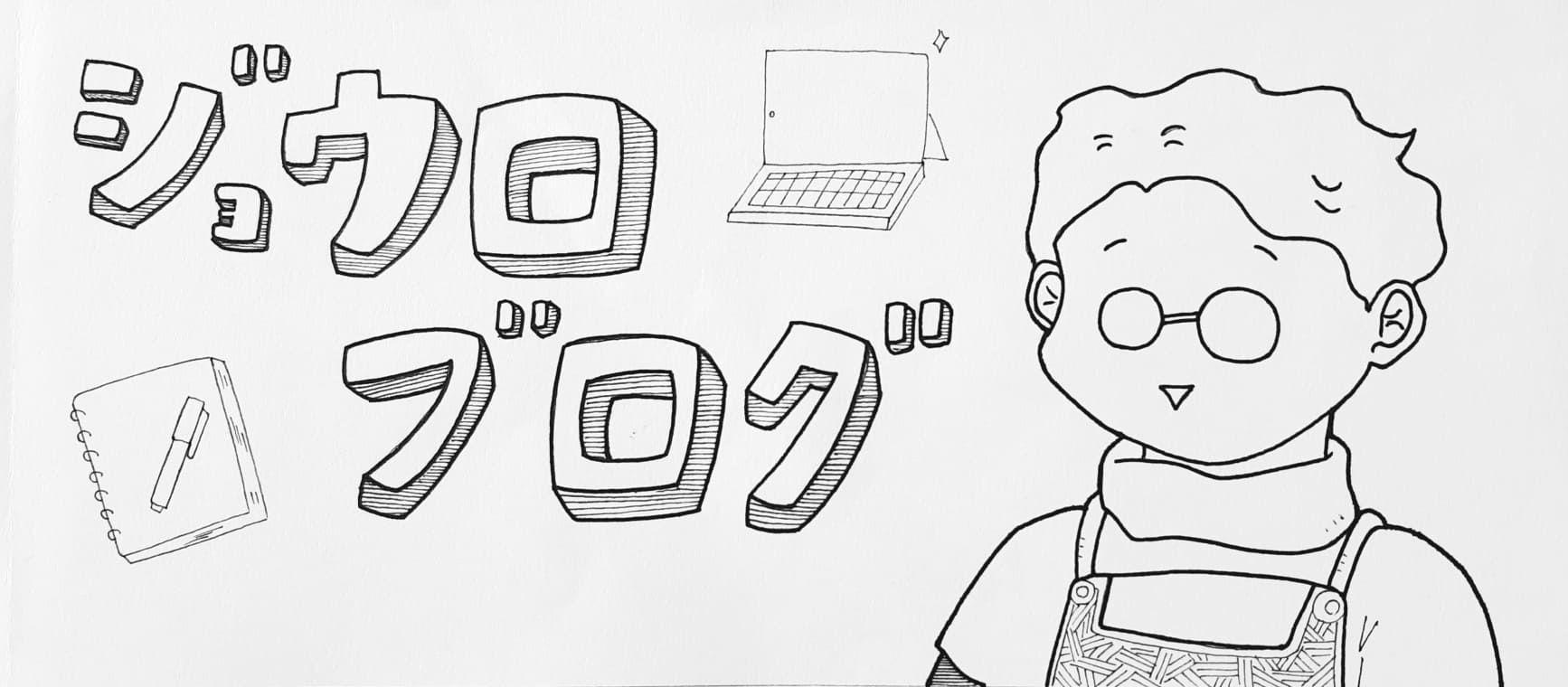







コメント