子育てや保育の現場でよく耳にする「療育」という言葉。けれど、「療育」と聞いて、すぐにどんなものなのか、イメージできる人は少ないかもしれません。また、「療育」と言うと、つい「障がいがある子ども」のための支援だと思う人も多いかもしれませんが、実はそうではありません。
このブログでは、療育がどういったものかを解説し、「療育=障がい者」ではないという点について、特に丁寧に説明したいと思います。子育て世代や保育職に就いている方々に、療育について理解を深めてもらえたらうれしいです。
療育とは?どんな目的があるの?
療育とは、発達に課題がある子どもたちが、自分のペースで成長していくための支援を受けるための場や活動のことを指します。療育の目的は、子どもたちが持っている発達の特性に合わせて、必要なスキルや経験を積むことで、より良い生活や社会参加ができるようにすることです。
療育が提供する支援は多岐にわたります。例えば、言葉の発達に遅れがある子には、ことばを使ったコミュニケーションの練習が行われます。また、運動能力や感覚に偏りがある子には、感覚統合療法や運動のトレーニングを通じて体の使い方を学びます。さらに、社会的なスキルが足りない子には、友達との関わり方や集団でのルールを学ぶ支援が行われます。
つまり、療育は「その子が今、足りていない部分を補い、その子らしい力を育てる」ことを目的としています。それぞれの子どもに合わせた支援を行うため、一人ひとりの状況に応じた方法が選ばれます。
療育=障がい者ではない
「療育」という言葉を聞いたとき、多くの人が「障がいを持っている子どものための支援」というイメージを持っているかもしれません。しかし、実際には、療育は必ずしも障がいを持つ子どもだけのためのものではありません。
たしかに、療育を受ける子どもの中には、「発達障がい」と診断された子どももいます。例えば、自閉症スペクトラム障がい(ASD)や注意欠陥・多動性障がい(ADHD)、学習障がい(LD)などの診断がついている子どももいるでしょう。でも、それがすべてではありません。
療育を受ける子どもたちの中には、診断を受けていないけれども、発達の特性が少しずつ違う子どももたくさんいます。たとえば、言葉の発達が遅れている、社会性や集団での行動が苦手、感覚の過敏さがある、といった特徴がある子どもたちです。このような子どもたちは、「発達に少し遅れがある」「成長のペースが異なる」というだけで、必ずしも障がいがあるわけではありません。
だからこそ、「療育=障がいを持った子どもたち」ではないことを理解しておくことが大切です。療育は、発達に何かしらの課題がある子どもたちが、その特性に合わせた支援を受けるための場であり、障がいがあろうとなかろうと、発達に偏りがある子どもたちにとって非常に役立つサポートを提供する場所だと言えます。
療育が役立つ子どもたちの例
では、実際にどんな子どもたちが療育を受けるのでしょうか。以下に、療育を受けることが有益な子どもたちの例を挙げてみます。
- 言葉の発達が遅れている子ども
例えば、同じ年齢の子どもたちと比べて、言葉を話すのが遅い場合。お子さんがまだ「言葉が出ない」「コミュニケーションが取れない」と感じたら、言葉の教室で発音や言葉の理解を助ける支援を受けることができます。
- 社会性や集団生活が苦手な子ども
集団の中で他の子どもたちとうまく関わることが難しい子どももいます。お友達との遊びがうまくできない、集団でルールを守るのが苦手、気持ちをうまく伝えられない、などの問題がある場合、療育を通じて社会性を身につけることができます。
- 体の動かし方が不器用な子ども
運動が苦手で、手先が不器用だったり、バランスを取るのが難しかったりする子どももいます。そんな子どもたちには、感覚統合療法や運動療育を通じて、体の動かし方を学び、発達を助けることができます。
- 特定のこだわりが強い子ども
ある特定のものに強いこだわりがある場合、そのこだわりが日常生活に支障をきたすことがあります。療育では、そのこだわりの理解を深め、他の遊びや活動に興味を持たせる支援が行われます。
親や保育士ができること
親や保育士は、子どもたちの発達を支える上でとても重要な役割を担っています。療育が必要かどうかの判断は、最終的には親の判断ですが、周囲のサポートが大きな力になります。
- 親が気づいたら、早めに相談を
もし、子どもの発達に不安を感じたら、まずは保育士や幼稚園の先生、または医師に相談してみるとよいでしょう。療育を受けることで、早い段階から支援を受けることができるため、子どもにとっても大きな助けとなります。
- 保育士の役割
保育士や先生は、子どもたちの発達を日々観察しており、何かしらの特性や課題に気づくことが多いです。もし、子どもが集団生活で困っている様子や、発達の遅れが見られる場合、親に適切なタイミングで声をかけ、専門家との相談を勧めることが大切です。
最後に
「療育」とは、発達に少しずつ偏りがある子どもたちが、その特性に合わせて支援を受け、成長できるための場です。障がいがあるかないかにかかわらず、発達に困りごとがある子どもたちにとって、療育は非常に有益なサポートとなります。親や保育士としては、子どもが困っていることに気づき、早い段階で適切な支援を受けられるようにサポートしていくことが大切です。
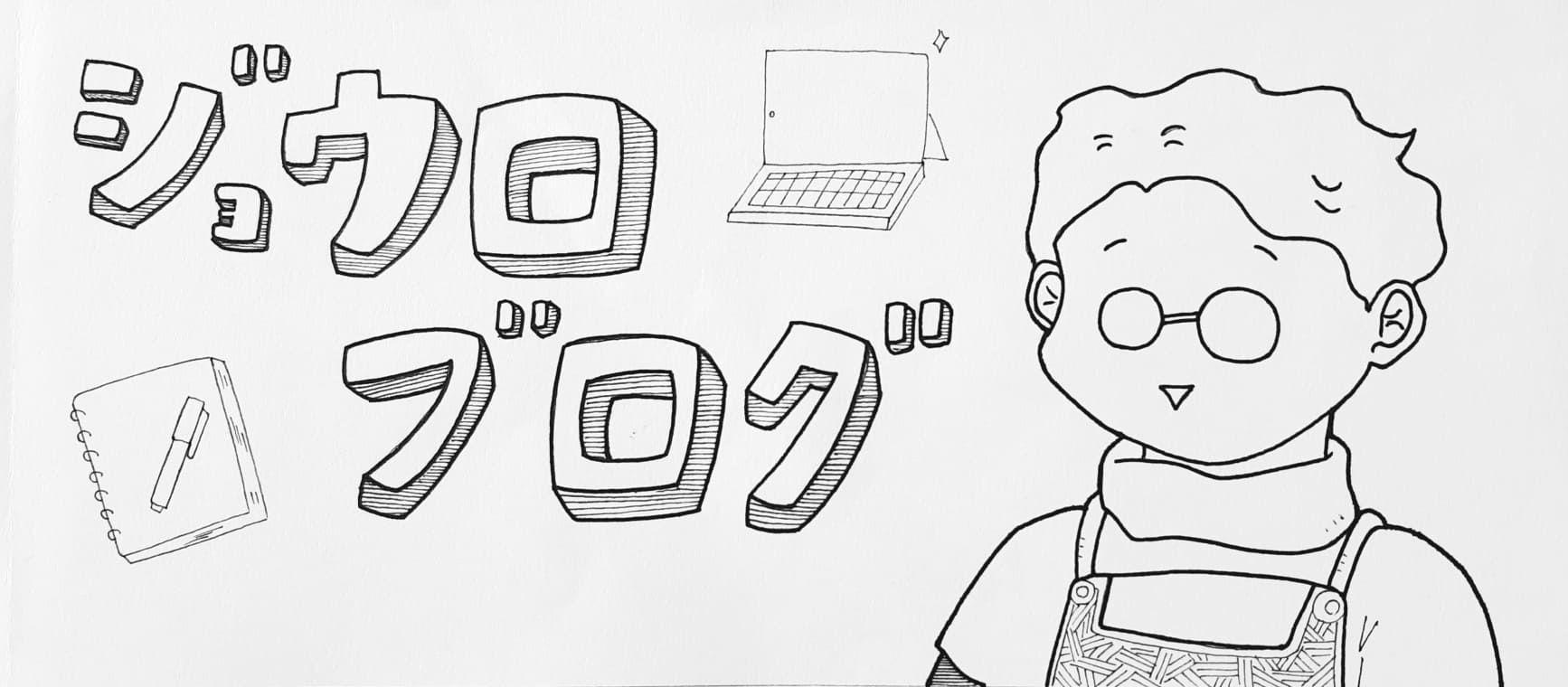







コメント