「先生、爪が伸びてるから切ってください!」
子どもにそんなふうに言われた経験がある先生もいるかもしれません。でも実は、保育士は基本的に 子どもの爪を切ることはできません。
保育園やこども園で働く中で、「爪が伸びていて危ないな」と思うことはよくあります。引っかいてしまったり、爪の間に汚れがたまったり、心配になる場面もあるでしょう。
この記事では、「なぜ保育士は爪を切ってはいけないのか?」という理由と、園でできる対応策についてわかりやすくまとめます。
保育士が子どもの爪を切れない理由とは?
医療行為と見なされるおそれがある
子どもの爪を切るというのは、一見すると日常的なことに思えます。でも、実はこれが医療行為にあたる可能性があるのです。
とくに、誤って出血させてしまった場合、「なぜ園でそんなことをしたのか」と問題になることも。保育士は医療資格をもっていないため、基本的に爪を切るなどのケアは保護者にお願いするのがルールです。
安全面のリスクがある
小さい子どもは、じっとしているのが苦手です。爪切りの最中に急に動いてしまったり、嫌がって手を引っこめたりすることもあります。
もし傷をつけてしまったら…その瞬間に信頼関係が崩れることもありますし、保護者からのクレームにつながることもあります。
保護者との価値観のズレ
ある家庭では「爪は深めに切る派」、またある家庭では「ヤスリで整える派」など、家庭ごとにケアのしかたが違うことも多いです。
園の先生が良かれと思って爪を切っても、「うちではそうしてないのに」と言われることがあるのです。とくに、爪の形や長さにこだわりがある保護者もいるため、慎重に対応する必要があります。
保育士の業務外であること
保育士の主な仕事は、子どもの 育ちを見守り、生活や遊びを支えること です。爪切りなどの身体的なケアは、基本的には家庭の役割とされています。
園としても、「うちでは爪は切りません」とルールとして明記しているところが多くあります。
爪が伸びている子どもへの対応策は?
「でも、実際に爪が伸びていて危ないときはどうすればいいの?」
そんなときに、保育士としてできる対応を紹介します。
保護者にやんわり伝える
まず一番大切なのは、保護者にていねいに伝えることです。
たとえば…
「最近、○○ちゃんの爪が少し長めなので、けがの予防のためにおうちで見ていただけますか?」
こんなふうに、責めるような言い方ではなく、「安全のためにお願いしますね」という気持ちを込めて伝えると、角が立ちにくくなります。
「何度言っても変わらない」というときも、定期的にやんわりと声をかけ続けることが大切です。
子どもに気づかせる声かけ
年中・年長くらいになってくると、自分の体のことに少しずつ関心が出てきます。
「お友だちの顔をひっかいちゃったら痛いよね」
「爪の間にばい菌が入っちゃうかも」
そんなふうに、爪を短く清潔にしておく理由をわかりやすく伝えることで、子ども自身が気にするようになることもあります。
ときには「おうちでママに爪切ってもらってね」と、自分から言えるように促すのも良い方法です。
手洗いや清潔を保つ
爪が伸びていることで一番こわいのは、不衛生になってしまうことです。
爪の間には汚れがたまりやすく、そこからばい菌が入ることも。だからこそ、爪の状態に関係なく 手洗いをていねいに行うことがとても大切です。
手のひら、指先、爪の間までしっかり洗う習慣をつけることで、清潔を保つことができます。
幼児の爪切りのコツ
家庭で爪を切るときに「じっとしてくれない」「嫌がる」など、苦労する保護者も多いですよね。ここでは、幼児の爪切りをスムーズにするコツを紹介します。
お風呂上がりに切る:爪がやわらかくなり、切りやすくなります。
リラックスしているときに行う:寝ている間や、テレビを見ているときなど、気をそらしながら切るのがコツです。
少しずつ切る:一度に全部切ろうとせず、気づいたときに少しずつ切るのも効果的。
やすりを使う:爪切りが怖い子には、やすりで整える方法もあります。
楽しい雰囲気にする:「爪さん、バイバイしようね!」など、声かけを工夫するのもおすすめ。
保護者が「面倒だから後回しにしがち」な場合は、こうしたコツを伝えてあげると、家庭でもスムーズにケアできるかもしれません。
まとめ|保育士は「爪を切る」より「気づいて伝える」役割
保育士は、子どもの爪を切ってはいけない――これは決まりではありませんが、安全・衛生・信頼関係を守るための基本的なルールです。
大切なのは、「爪が伸びているから切る」のではなく、
「子どもの安全のために、保護者と協力して整えていく」姿勢です。
爪が伸びていたら、「切る」ではなく「伝える」。
保育の中でできること、家庭でお願いすること。その線引きをしっかり持って、子どもたちの健康と安全を守っていきましょう。
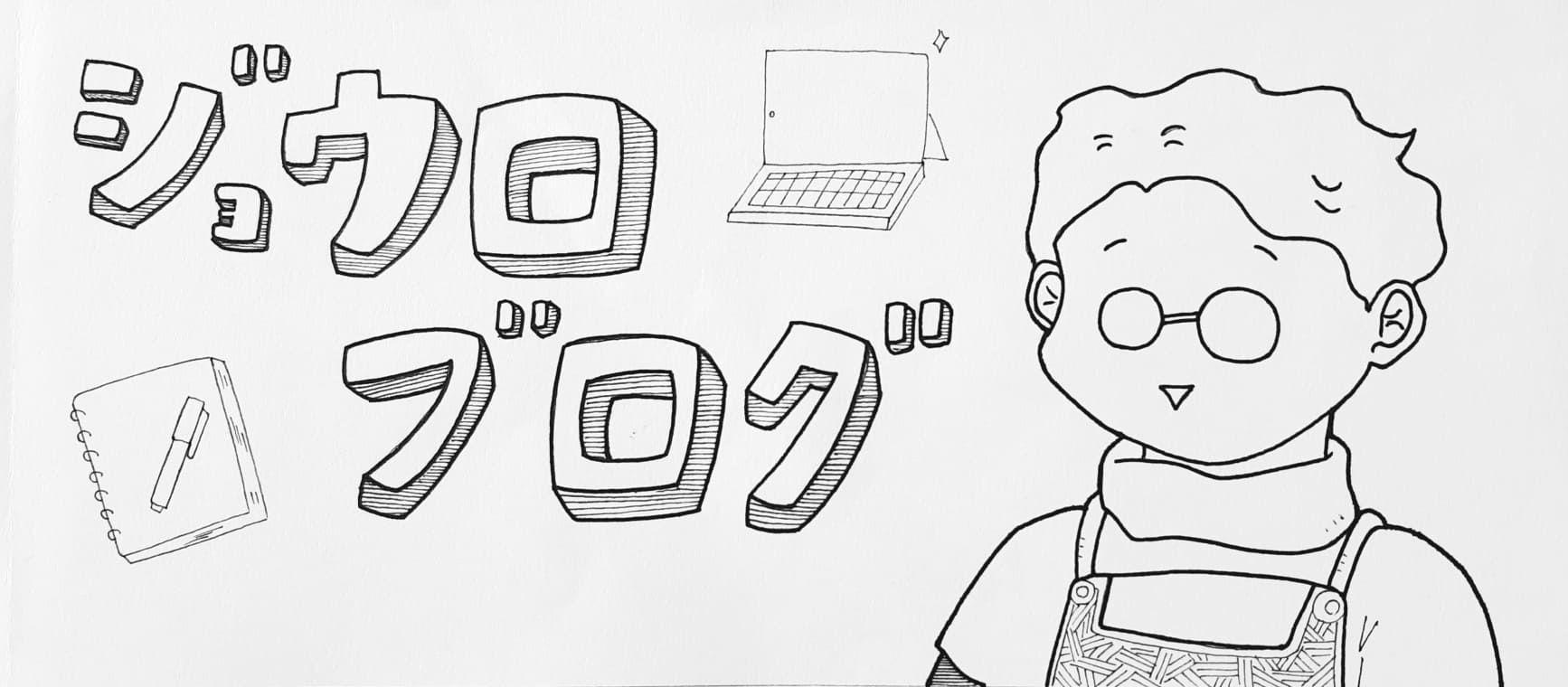







コメント