言葉を選ぶ時代の難しさ
「それって、○○ハラスメントじゃない?」
そう言われる機会が増えてきたように感じます。時代とともに、誰かを傷つけないようにという配慮が広まり、言葉や関わり方への意識が高まってきました。
それ自体はとても良いこと。でも一方で、私たちはどこか「何を言ったらハラスメントになるのか」とビクビクしながら話すようになっていないでしょうか?
子どもたちと向き合う保育や教育の現場でも、その空気は強く感じられます。「傷つけたくない」と思うほどに、言葉が遠回りになったり、伝えること自体をためらったり。時にその迷いが、子どもとの関係を“薄く”してしまうこともあるのです。
ハラスメントの種類と、広がる境界線
現代では、ハラスメントの種類が100を超えるとも言われています。たとえば……
パワハラ(立場を利用した圧力)
セクハラ(性的な言動)
モラハラ(精神的な支配・攻撃)
マタハラ(妊娠・出産に関する差別)
アルハラ(飲酒の強要)
エイハラ(年齢による差別)
カスハラ(カスタマーハラスメント)
さらには、リモハラ(リモートワーク時の圧力)やヌーハラ(麺をすする音)など、日常のあらゆる場面に「ハラスメント」という名前がつけられています。
もちろん、どれも「誰かを不快にさせた経験や痛み」から生まれた言葉です。ですが、あまりにも細分化され、曖昧なラインが増えていくと、「これは言っていいのか?」と迷い、結果として“言わない”ことを選ぶようになります。
言えない空気が、子どもとの距離を生んでいく
保育や子育ての現場では、この「言えない空気」が思いがけない影響を与えることがあります。
叱ることを避ける
自由を優先しすぎて介入を控える
「見守る」と「放任」の境目がぼやける
もちろん、怒鳴る・押しつける・否定するなどの行為は避けるべきです。でも、だからといって「何も言わない」ことが正解なのでしょうか?
大人が関わらないことで、子どもが「放っておかれている」「見てくれていない」と感じてしまうこともあるのです。
それでも、伝えなければいけないことがある
子どもたちは、今この瞬間だけでなく、これから長い人生を歩んでいきます。時には耳が痛くても、今伝えておいたほうがいいことがあります。
相手の気持ちを考えること
命を大事にすること
間違えたときにどう向き合うか
それらは、単なる知識やしつけではなく、「その子の未来」をつくっていく大事な要素です。だからこそ、私たちは言葉を尽くして、思いを届ける努力をやめてはいけないのだと思います。
ハラスメントにならないために——大人ができる準備と工夫
大切なのは、「どう言うか」よりも「どれだけその子を見ているか」。信頼関係があるかどうかで、同じ言葉でも受け取られ方は大きく変わります。
普段から対話の時間を大切にする
子どもの気持ちに耳を傾ける
指摘の前に、その子のよい面に目を向ける
一度でわかってもらおうとせず、繰り返し伝える
また、「あなたはどう思う?」と問いかける姿勢を持つことで、子ども自身の考える力を引き出しつつ、関係性の土台を育てていくことができます。
ふりかえりと対話の力
私たちの伝えた言葉が、いつも100%正しく伝わるわけではありません。だからこそ、「ちゃんと届いているかな?」とふりかえり、自分の言葉を振り返ることも大切です。
傷つけてしまったかもしれない
言い過ぎてしまったかもしれない
伝え方を間違えたかもしれない
そんな時は、素直に謝ったり、もう一度話し合ったりする“リペア(修復)”の姿勢が、関係性をより強く、深いものに変えてくれます。
子どもたちは、大人の「完璧さ」よりも、「本気のまなざし」や「まっすぐな対話」を見ています。
名前をつけすぎた社会で、名前のない思いを伝えるということ
ハラスメントという言葉は、必要な概念です。誰かが傷つけられる社会ではいけません。
でも、名前ばかりを気にして、本当に伝えたい思いや願いが埋もれてしまっては本末転倒です。
言葉は、ときに誤解され、ときに誤ってしまうものです。それでも、関係性を大切にしながら、言葉を尽くしていくこと。それが、こどもたちの育ちに向き合う大人の覚悟なのではないでしょうか。
“これはハラスメントになるか?”ではなく、
“これは、その子の未来のために必要な言葉だったか?”
その問いを胸に、これからも私たちは、子どもたちにまなざしを向けていきたいと思います。
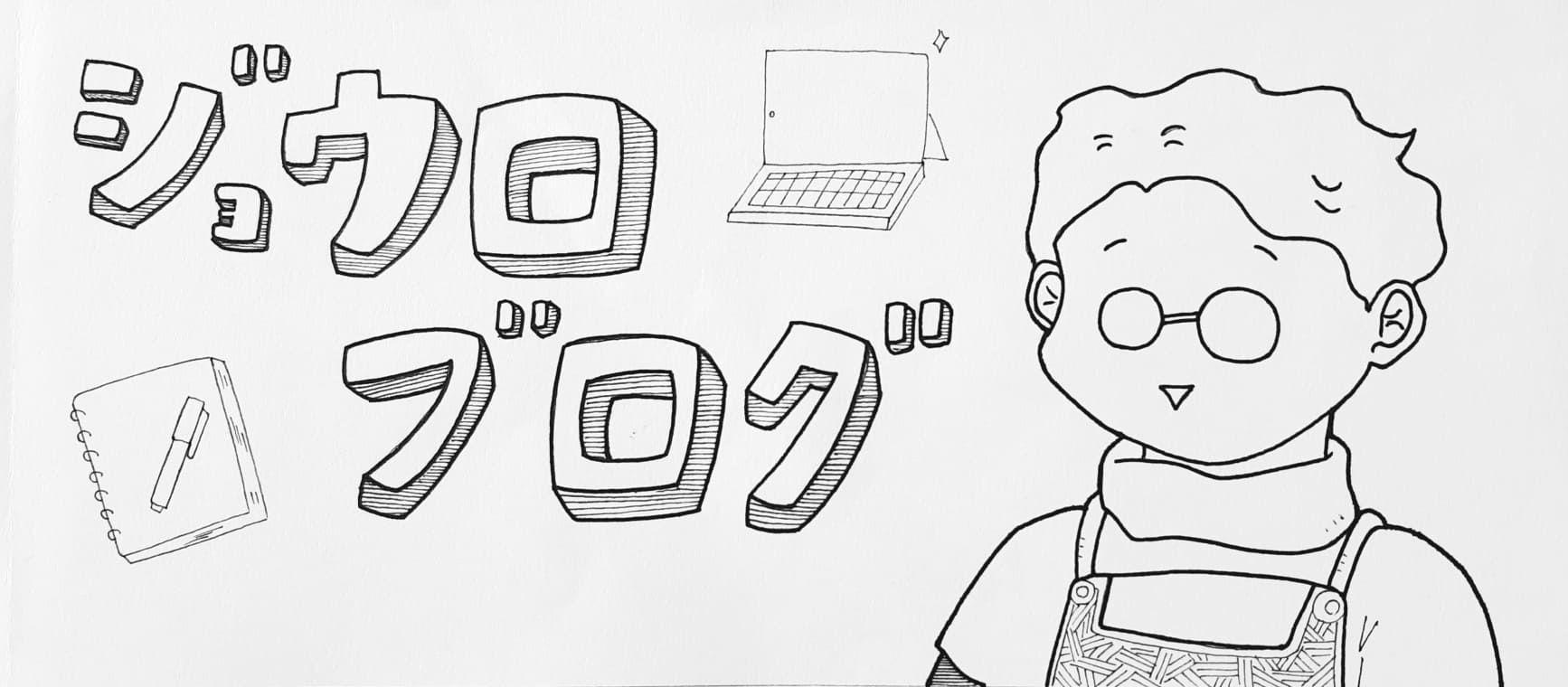




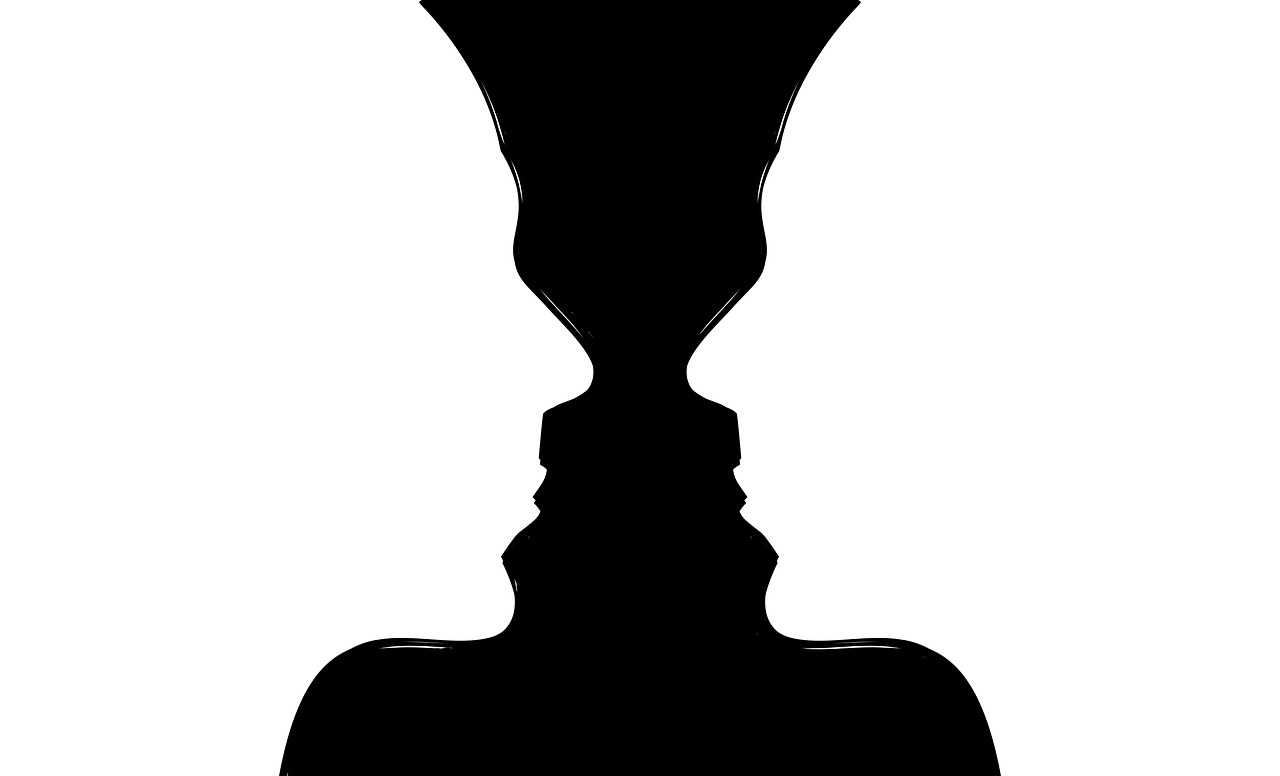


コメント