- 子どもの行動はどうすれば変わる?
「子どもに何度言っても行動が変わらない…」こんな悩みを持つ保育者や親は多いのではないでしょうか?
子どもが片付けをしない、順番を守れない、友達に優しくできない…。そんなとき、大人は「もっと強く言う」「ご褒美を用意する」などの方法を試しますが、それだけではなかなか続かないこともあります。
実は、心理学の法則をうまく活用すると、子どもが自然と良い行動をとるようになることがあります。そのヒントになるのが、ロバート・B・チャルディーニの著書『影響力の武器』です。この本では、人が無意識のうちに影響を受ける心理的な法則がいくつか紹介されています。
その中の一つが、「一貫性とコミットメントの原理」です。
これは、「人は自分の言動に一貫性を持ちたがる」という心理を利用したもの。たとえば、ある子どもが「ぼく、お片付けできるよ!」と口にしたとします。すると、その子は「自分は片付けができる子だ」というイメージを持ち、それを維持しようとするため、進んで片付けをするようになるのです。
この原理をうまく保育や子育てに活かせば、子どもたちは無理なく良い行動を続けられるようになります。そこでこの記事では、「一貫性とコミットメントの原理」を子どもの行動に活かす方法について、具体的な活用例や注意点を紹介していきます。
- 「一貫性とコミットメントの原理」とは?
「一貫性とコミットメントの原理」は、「人は自分の発言や行動に一貫性を持とうとする」という心理を利用したものです。
たとえば、大人でも「毎日ランニングする!」と宣言したら、それを守ろうと努力しますよね? これは、周りに言った手前、やらなかったときに「一貫性がない」と思われるのが嫌だからです。この心理は、子どもにも働きます。
子どもが「ぼくはお片付けできるよ!」と言ったら、それを守ろうとする。つまり、「子どもに小さな約束をさせる」「ポジティブなラベリングをする」ことで、良い行動を引き出せるのです。
では、具体的にどう活用すればいいのか?次の章で5つの方法を紹介します。
- 子どもの良い行動を引き出す5つの具体的な方法
① ポジティブなラベリングを活用する
「〇〇くんは優しいね!」と言われると、子どもは「自分は優しい子なんだ」と思い、そのイメージに合わせた行動をとるようになる。
例えば、「お片付けができる子だね!」と言われた子は、片付けを進んでやるようになる。
→ ただし、ラベリングのプレッシャーにならないように、行動にフォーカスして伝えることが大切!(詳しくは後述)
② 小さな約束を積み重ねる
いきなり「毎日片付けしようね!」と大きな約束をさせるのではなく、小さな成功体験を積み重ねる。
例:「このおもちゃだけ片付けてみよう!」→ 「できたね!じゃあこっちも!」
こうすることで、「自分は片付けができる」という意識が芽生え、自然と行動が定着する。
③ 子ども自身に目標を決めさせる
大人が決めたルールより、自分で決めた目標のほうが守りやすい。
例:「今日の遊びで何か1つ頑張ることを決めよう!」
こうすると、「やらされている」のではなく、「自分で決めたことだから頑張る」という気持ちになりやすい。
④ 「〇〇してくれて助かるな!」と感謝を伝える
「先生が喜ぶからやる」のではなく、「自分の行動が役に立つ」と思えるようにする。
例:「〇〇くんが片付けしてくれたから、先生助かったよ!」
こうすることで、子どもが主体的に行動できるようになる。
⑤ できたことを言葉にして振り返る
帰りの会などで「今日できたこと」を共有すると、成功体験が強化される。
例:「お友だちを助けた子がいたね」「元気に挨拶できた子がいたね」
これを続けることで、子どもたちは「自分はこういう行動をする子なんだ」と意識するようになる。
- 使うときの注意点
① 「良い子」プレッシャーをかけすぎない
「〇〇くんは優しい子!」と言いすぎると、「いつも優しくしなきゃ」とプレッシャーになってしまう。
→ 「優しくしてくれてうれしいな!」 のように、行動にフォーカスして伝える。
② 無理に約束をさせない
「次もちゃんとできるって約束して!」と強制すると負担になる。
→ 「今日みたいにできたらいいね!」と軽く投げかけるくらいがちょうどいい。
③ 失敗しても責めない
「できる子だよね?なんで今日はできないの?」と責めると逆効果。
→ 「今日は疲れちゃったかな?また次やってみよう!」とフォローする。
- まとめ|「できる子」ではなく「できる行動」に注目しよう
「一貫性とコミットメントの原理」をうまく活用すると、子どもたちは自然に良い行動をとるようになります。
しかし、無理に押し付けたり、プレッシャーをかけすぎると逆効果になることも。大切なのは、「できた!」という成功体験を積み重ねることです。
「できる子」ではなく、「できる行動」に目を向けることが、子どもたちの成長につながります。ぜひ、保育や子育ての中で、無理なく取り入れてみてくださいね!
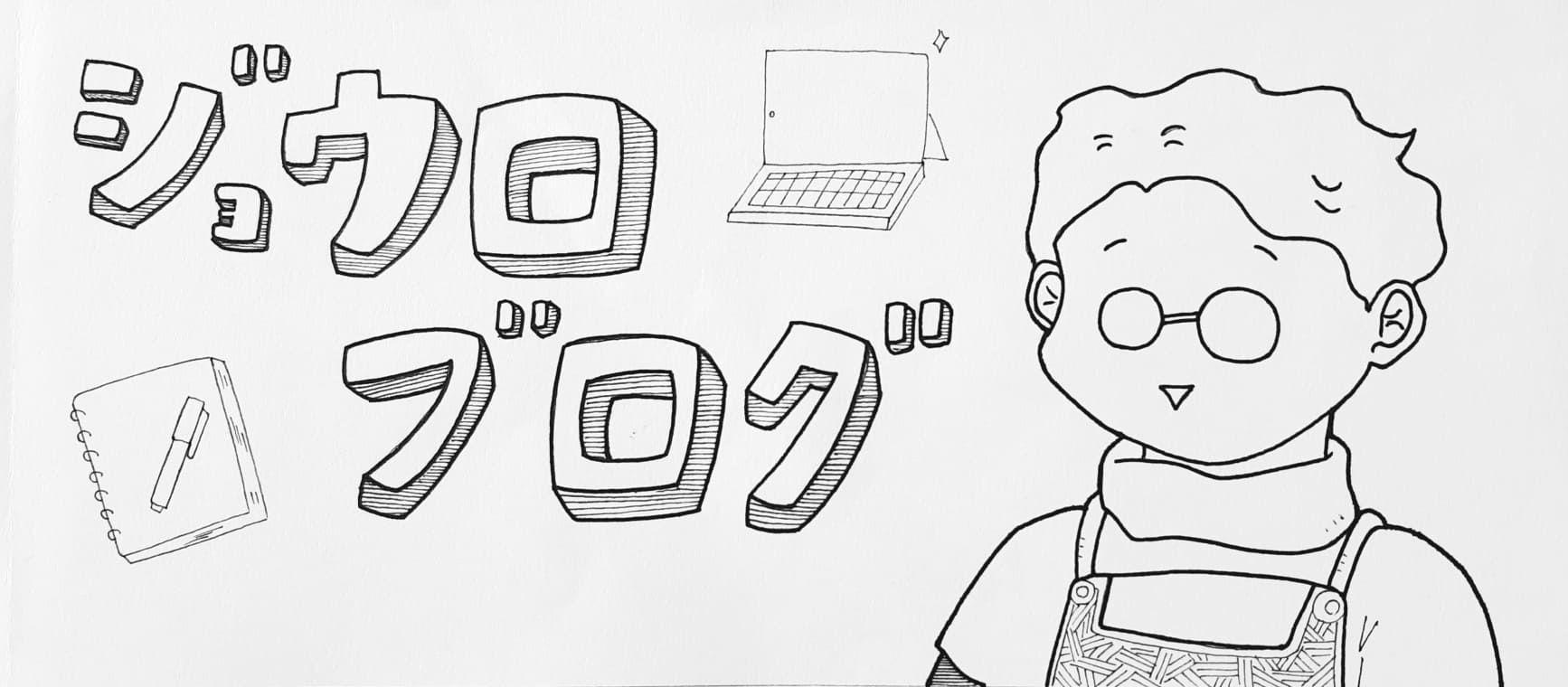







コメント