近年、「グレーゾーンの子どもたち」という言葉を耳にすることが増えてきました。発達に気になるところがあるけれど、診断がつかない、または診断基準ギリギリの子どもたちのことを指します。
「育てにくさを感じるけど、発達障害とは診断されていない」
「周りの子と少し違うけど、具体的な支援が受けられない」
そんな悩みを抱える保護者や、現場で子どもたちと向き合う先生たちが増えています。今回は、グレーゾーンの子どもたちの特徴や、日本での割合、種類、そして未就学児への対応についてお話しします。
グレーゾーンの子どもたちの割合は?増えているの?
日本では、グレーゾーンの子どもたちがどれくらいいるのか、正確なデータはありません。しかし、ある調査では全体の約15%(約6~7人に1人)がグレーゾーンに該当する可能性があると言われています。
また、文部科学省のデータによると、通常学級にいる小中学生の約8.8%が発達障害の可能性が高いと報告されています。この数字が年々増えている背景には、発達障害に対する理解が進み、気づかれるケースが増えたことが関係しています。
ただ、ここで大事なのは「発達障害の子どもが増えた」というよりも、「これまで見過ごされていた困りごとが、ようやく認識されるようになった」と考えたほうが良さそうです。
グレーゾーンにはどんな種類があるの?
グレーゾーンの子どもたちは、一人ひとり違う特徴を持っていますが、大きく分けると次のようなタイプがあります。
- 発達障害のグレーゾーン
発達障害の診断基準には当てはまらないけれど、似たような特徴がある子どもたちです。
ASD(自閉スペクトラム症)のグレーゾーン
コミュニケーションが苦手だけど、特定の友だちとは仲良くできる
こだわりが強いけど、日常生活に大きな影響はない
ADHD(注意欠如・多動症)のグレーゾーン
集中力にムラがあり、興味のあることには没頭できる
忘れ物が多いけど、環境を工夫すれば対処できる
LD(学習障害)のグレーゾーン
読み書きが苦手だけど、他の能力でカバーできる
計算が遅いけど、日常生活ではそこまで支障がない
- 知的発達のグレーゾーン
知的障害の診断基準(IQ70以下)には当てはまらないけれど、学習や生活の中で困難を感じるケース。「ボーダー知能(IQ70〜85)」と呼ばれることもあります。
- 精神的なグレーゾーン
発達障害ではなくても、繊細な気質や生活リズムの乱れによる困りごとを抱える子どもたちもいます。
HSP(敏感すぎる気質)
感覚が鋭く、人混みや大きな音が苦手
感情が不安定で、ちょっとしたことで傷つきやすい
起立性調節障害(OD)のグレーゾーン
朝起きるのが苦手で、学校に行けないことがある
体調の波が激しく、疲れやすい
不登校のグレーゾーン
学校に行くのがしんどいけど、完全に行けないわけではない
特定の授業や人間関係にストレスを感じる
グレーゾーンの未就学児への対応
未就学の子どもたちの場合、「まだ成長の途中だから様子を見よう」と思うこともあるかもしれません。でも、ちょっとしたサポートでぐんと過ごしやすくなることもあります。
- 家庭でできること
生活リズムを整える
決まった時間に寝る・起きる・食べることで、心と体の安定につながる。
短くわかりやすい声かけ
「ちゃんとして!」ではなく、「靴をここに置こうね」など具体的に伝える。
視覚的なサポート
予定やルールを絵や写真で示すと理解しやすい(「おしたくボード」など)。
成功体験を増やす
「できたね!」と小さな成功を積み重ねて、自信を持たせる。
- 保育園・幼稚園での対応
環境の調整
大きな音や人混みが苦手な子には、静かなスペースを用意する。
少人数での活動を増やす
集団行動が苦手な子には、小グループで遊ぶ時間を作る。
遊びを通じて発達を促す
ブロックやお絵かきで指先の動きを鍛えたり、ごっこ遊びで社会性を学んだりする。
- 専門機関の活用
発達相談窓口(自治体)
市区町村の保健センターなどで相談できる。
児童発達支援センター・療育施設
言葉の発達やコミュニケーション力を伸ばすプログラムを受けられる。
医療機関(小児神経科・発達外来)
必要に応じて専門医の診察を受け、具体的な支援を考える。
まとめ:一緒にできることから始めよう
グレーゾーンの子どもたちは、発達障害の診断がつかない分、支援の枠に入りづらく、家庭や保育・教育現場でのサポートがとても大切になります。
でも、「何かしなきゃ!」と焦る必要はありません。まずはその子に合った環境を作ることから始めてみましょう。小さな工夫で、子どもたちがもっと楽しく、安心して過ごせるようになります。
グレーゾーンの子どもたちが増えている今、私たち大人ができることを少しずつ実践しながら、一緒に子どもたちの未来を支えていきませんか?
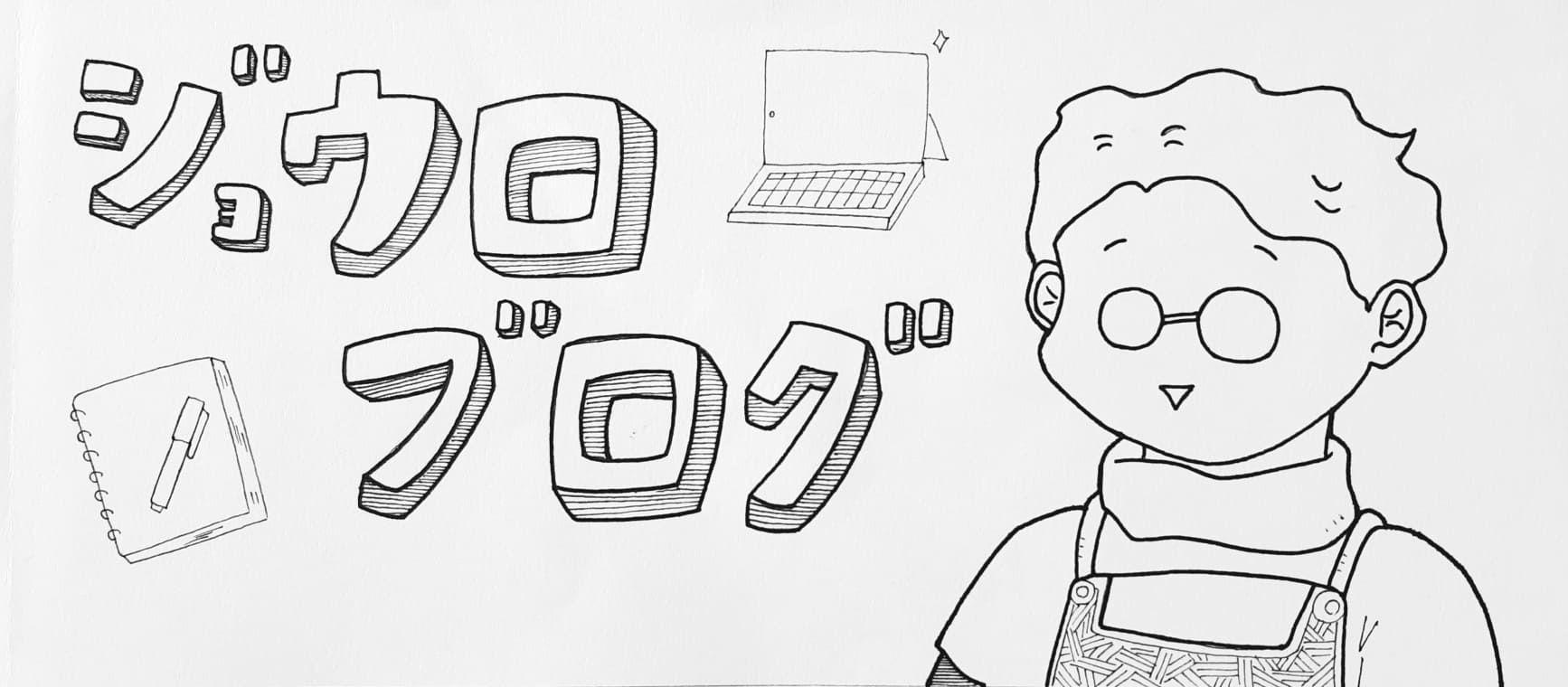







コメント