- 「なんで言うこと聞いてくれないの…?」
「片付けなさい!」
「ご飯の前に手を洗って!」
「順番を守ろうね!」
子どもに何かを伝えても、なかなか思うように動いてくれないことってありますよね。
「なんで素直にやってくれないの?」と思うこともあるかもしれません。
でも、ちょっと思い出してみてください。
先生や親が楽しそうに片付けを始めると、子どももつられて動き出すこと、ありませんか?
実はこれ、心理学で「返報性の原理」と呼ばれる法則が働いているんです。
今回は、この「返報性の原理」がどんなもので、どう活かせるのかをお話しします!
- 返報性の原理って何?
「返報性の原理」とは、「人は何かをしてもらうと、お返しをしたくなる」 という心理のこと。
アメリカの心理学者ロバート・チャルディーニが『影響力の武器』で紹介した考え方です。
例えば…
スーパーで試食をもらうと、なんとなく買いたくなる
友達にプレゼントをもらうと、自分も何か返したくなる
道を教えてもらうと、お礼を言いたくなる
「してもらったら、お返ししたくなる」という、ほぼ本能レベルの心理なんですね。
この法則、実は子育てや保育でもめちゃくちゃ使えるんです!
- 保育・子育てでの応用テクニック
「返報性の原理」を知っていると、子どもを無理やり動かすのではなく、自然と「やりたくなる」流れを作ることができます。
① 片付けを「やりたくなる」仕掛け
例えば、子どもに「おもちゃを片付けなさい!」と言っても、なかなか動かないことが多いですよね。
でも、先生や親が片付けを始めると、子どもが自然と手伝い出すことがあります。
これは、子どもが「手伝ってもらったから、お返ししよう」と感じるから。
✔ 活用ポイント
「先生も片付けるから、一緒にやろう!」(巻き込む)
「○○くんが積み木を片付けてくれたら、先生もブロックを片付けるね!」(交換の形にする)
こうすると、子どもは「やらされる」のではなく、「自分もやりたい」と思うようになります。
② 友だちとの助け合いを増やす
「返報性の原理」は、子ども同士の関係作りにも活かせます。
例えば…
「○○ちゃん、困ってたから△△くんが助けてくれたんだよ」
「○○ちゃんが貸してくれたから、次は△△くんが貸してあげようね」
こう言われると、子どもは「今度は自分も誰かを助けよう!」と感じるんです。
✔ 活用ポイント
「○○くんが手伝ってくれたよ!」と伝える(感謝の可視化)
「ありがとうって言ってもらえたね!」とフィードバックする(喜びを共有)
「助けてもらうと、助け返したくなる」→ 助け合いの好循環が生まれる!
③ 「手洗い・食事の習慣」を楽しく定着させる
食事の前に手を洗う習慣、どうやって身につけさせよう?
こんなときも、返報性の原理が使えます。
✔ 活用ポイント
「先生も手を洗うから、一緒に洗おう!」(モデル行動)
「手を洗ってくれてありがとう!おかげでご飯がもっとおいしく食べられるね」(行動を肯定する)
子どもは「先生が一緒にやってくれたから、やろう!」と思うし、
「手を洗ってよかった!」という気持ちも強くなります。
- 保護者との信頼関係にも使える!
「返報性の原理」は、保護者対応にもめちゃくちゃ有効です。
例えば、普段からポジティブな声かけをしておくと、何かお願いしたいときに協力してもらいやすくなります。
✔ 活用ポイント
「今日は○○ちゃん、こんなことを頑張っていました!」と伝える(先に与える)
「お忙しいところすみません」と、先に気遣いの言葉をかける(配慮を示す)
こうすると、「普段から気にかけてもらってるし、こちらも協力しよう」という流れが生まれます。
- 実は歴史にもあった!上杉鷹山の知恵
この「返報性の原理」、実は昔から活用されていました。
例えば、江戸時代の名君・上杉鷹山。
彼は「倹約しなさい!」と命令するのではなく、まず自分が質素な生活を実践しました。
すると、人々は「鷹山様がここまでしているのなら、自分たちも…」と動いたのです。
これってまさに、「まず自分が行動すると、周りも動く」という返報性の原理そのもの。
子どもも大人も、誰かの行動を見て影響を受ける。だから、まずは自分から!
- まとめ:子どもが「やりたくなる」環境を作ろう!
✅ 「返報性の原理」は、「お返しをしたくなる」心理を活用するテクニック!
✅ 片付け、助け合い、習慣づけ、保護者対応…どこでも使える!
✅ 「まず自分がやる」「感謝を伝える」と、子どもが自然と動く!
「子どもがなかなか動いてくれない…」と悩んだら、ぜひこの考え方を試してみてください!
「命令する」のではなく、「自然と動きたくなる」環境を作ると、子育ても保育もぐっと楽しくなりますよ!


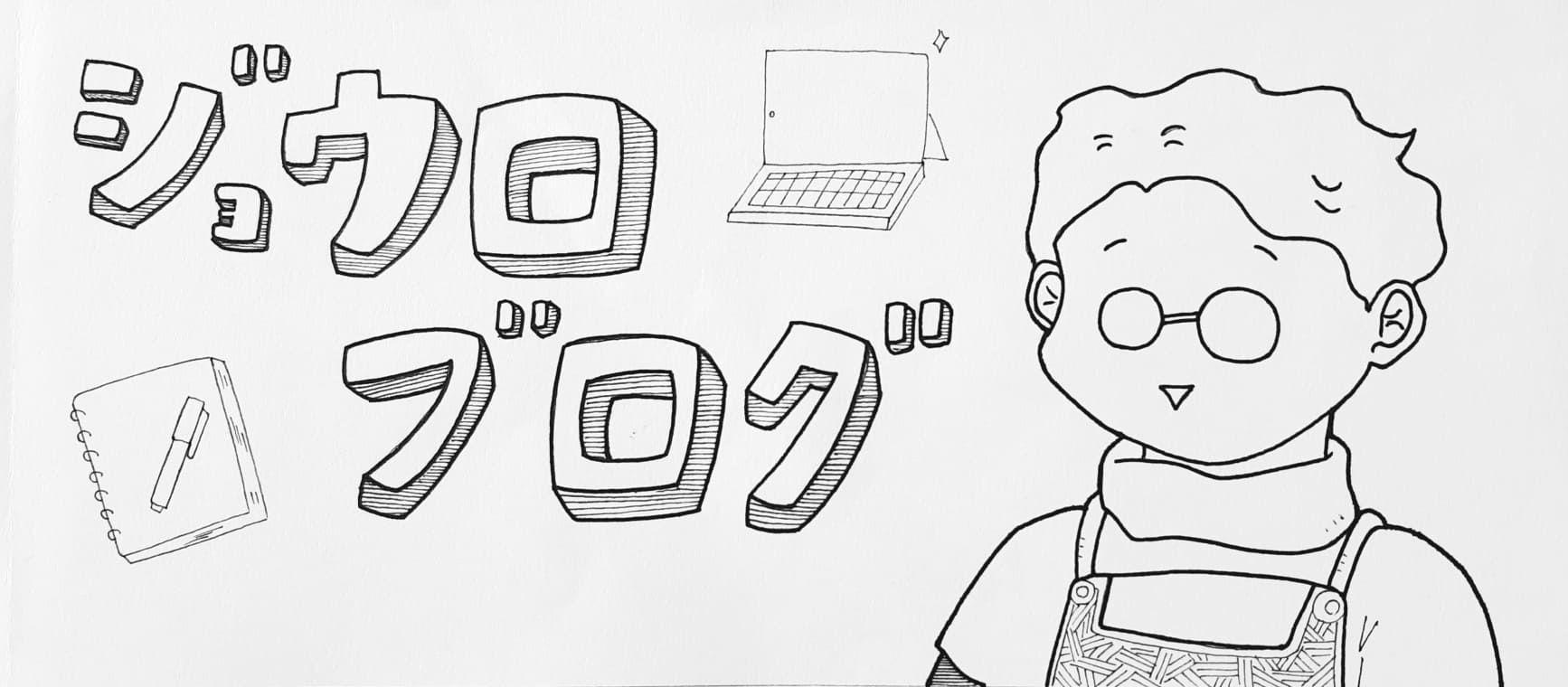







コメント